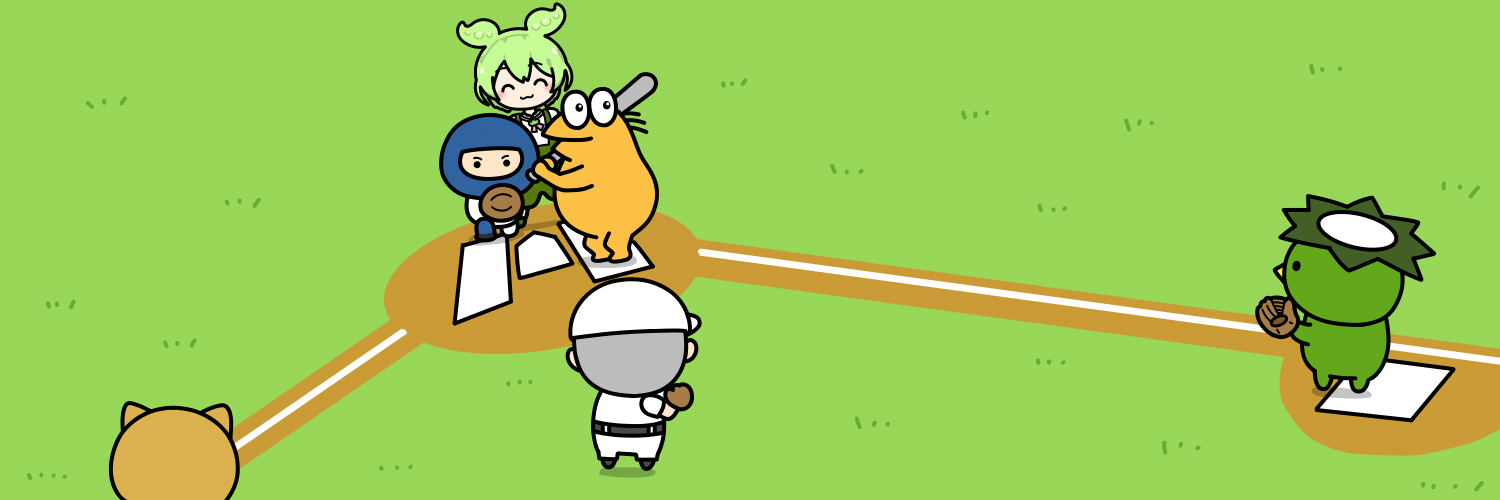ずん
「立ち食いそば屋の若女将が救世主って、これもう令和のシンデレラストーリーなのだ!」
やきう
「救世主って...朝7時半から立ちっぱなしで蕎麦茹でとるだけやんけ。大袈裟すぎやろ。」
でぇじょうぶ博士
「いやいや、これは深い話でやんす。麹町といえば永田町に隣接する超一等地でやんすが、実はランチ難民が多発する魔境でもあるでやんす。」
ずん
「え、東京のど真ん中なのにランチ難民っておかしくないのだ?」
でぇじょうぶ博士
「オフィス街特有の問題でやんす。昼時は一斉に人が溢れ出して、どの店も満席。待ち時間だけで貴重な昼休みが消えていくでやんす。まるでブラックホールに吸い込まれる時間のようでやんすね。」
かっぱ
「そこで立ち食いそば屋や。回転率エグいからな。サラリーマンにとっては時短の味方やで。」
やきう
「でも26歳の女が飲食未経験で若女将って、親のコネか何かやろ?どうせ。」
でぇじょうぶ博士
「そこが面白いポイントでやんす。記事によれば2023年開業ということは、彼女が25歳前後で参画したことになるでやんす。飲食未経験でカウンターに立つというのは、相当な覚悟と適応力が必要でやんす。」
ずん
「でも立ち食いそばなんて、誰でもできそうなのだ。茹でて、つゆ入れて、はいどうぞ!って感じじゃないのだ?」
かっぱ
「甘いわ!立ち食いそばはスピード勝負や。1秒の遅れが命取りになる世界やで。しかも出汁の味で全てが決まるんや。」
でぇじょうぶ博士
「その通りでやんす。立ち食いそば店の肝は、味と回転率の両立でやんす。朝7時半から営業するということは、おそらく朝5時台には仕込みを始めているでやんす。若い女性がその生活を続けるのは、並大抵の根性じゃないでやんすよ。」
やきう
「それでも所詮は蕎麦屋やろ。将来性あるんか?AIに仕事奪われるんちゃうか。」
でぇじょうぶ博士
「面白い指摘でやんすが、実は立ち食いそば業界は意外と堅調でやんす。コロナ禍でも比較的ダメージが少なく、むしろテイクアウト需要で伸びた店も多いでやんす。何より、人間が作る温かい食事への需要は、AIでは代替できない部分があるでやんすからね。」
ずん
「でも若女将って呼ばれるの、本人は嬉しいのかなぁ?ボクならもっとカッコいい肩書きが欲しいのだ。『蕎麦界のカリスマ』とか。」
やきう
「ていうか、記事が持ち上げすぎなんや。どうせ美人やから話題になっとるだけやろ。不細工やったら誰も記事にせんわ。」
でぇじょうぶ博士
「むむむ、それは偏見でやんすが、一理あるでやんす。いわゆる『美人立ち食いそば店員』というギャップが話題性を生んでいる側面は否定できないでやんす。ただし、それだけで常連が付くほど甘くないでやんすよ。」
ずん
「じゃあ、この若女将の何が凄いのだ?教えてほしいのだ。」
でぇじょうぶ博士
「まず、飲食未経験から2年足らずで店を支える存在になった適応力でやんす。そして、オフィス街という特殊な環境で、サラリーマンたちの胃袋と時間を同時に満たす技術を身につけたことでやんす。これは想像以上に高度なスキルでやんすよ。」
かっぱ
「確かにな。朝7時半から営業って、早朝出勤のサラリーマンや、朝ごはん抜きで来た奴らを掴んどるわけや。これは賢い戦略やで。」
やきう
「でも立ち食いそば屋なんて、将来どうするんや。一生そこで蕎麦茹でるんか?」
でぇじょうぶ博士
「そこが次の展開として気になるポイントでやんすね。このまま店を継ぐのか、独立して自分の店を持つのか、それとも飲食業界で別の道を歩むのか。26歳という年齢は、まだまだ可能性に満ちているでやんす。」
ずん
「ボクなら絶対に独立して、『ずん蕎麦』って店を出すのだ!インスタ映えする蕎麦を作って、バズらせるのだ!」
やきう
「ていうか、立ち食いそば屋でインスタ映えとか意味わからんわ。5分で食って出ていく場所やぞ。」
でぇじょうぶ博士
「しかし、Z世代の起業家精神という観点から見ると、この若女将の選択は興味深いでやんす。安定したサラリーマンの道ではなく、あえて飲食という厳しい世界に飛び込んだわけでやんすから。」
ずん
「でも、飲食業って大変そうなのだ。休みないし、給料安いし、クレーマー多いし...」
でぇじょうぶ博士
「その通りでやんす。飲食業界は離職率が高く、特に若い世代の定着率は低いでやんす。だからこそ、この26歳の若女将が2年以上続けているという事実自体が、ある意味で『救世主』たる所以なのかもしれないでやんすね。」
かっぱ
「要するに、継続は力なりってことやな。地道にコツコツやっとるから、常連がついてくるんや。」
やきう
「まあ、ワイも認めたるわ。朝7時半から働くとか、ワイには絶対無理やしな。尊敬するで。」
ずん
「じゃあやきうも立ち食いそば屋で修行してみたらどうなのだ?朝7時半起きなんて、ボクには絶対無理だけど、やきうなら...」
でぇじょうぶ博士
「結局のところ、この若女将が麹町の『救世主』と呼ばれる理由は、単に蕎麦を提供するだけでなく、忙しいサラリーマンたちに『安心感』を与えているからでやんす。毎朝同じ時間に同じ場所で、同じ味を提供する。これは都会で働く人々にとって、小さな心の拠り所になっているでやんすよ。」
ずん
「なるほど...深いのだ。でもボクは立ち食いそば屋じゃなくて、座って食べられるそば屋がいいのだ!」
かっぱ
「贅沢言うな。立って食う方が消化にええんやで。」
やきう
「ていうか、記事のタイトルが『救世主』って、盛りすぎやろ。せいぜい『便利な蕎麦屋のお姉さん』レベルやんけ。」
でぇじょうぶ博士
「確かに大袈裟な表現でやんすが、メディアというのはそういうものでやんす。ただ、彼女の存在が麹町のオフィスワーカーたちの日常を少しでも豊かにしているなら、それは立派な『救い』でやんすよ。」
ずん
「じゃあボクも誰かの救世主になりたいのだ!何をすればいいのだ?」
でぇじょうぶ博士
「まあまあ、ずん君。救世主になるには、まず誰かの役に立つことから始めるでやんす。この若女将のように、朝7時半から蕎麦を茹でるのも立派な社会貢献でやんすからね。」
ずん
「うーん...でもボクは朝7時半に起きるのすら無理なのだ。だからボクは夜の救世主になるのだ!深夜にラーメン屋でもやるのだ!」
でぇじょうぶ博士
「まあ、この記事から学べることは、年齢や経験に関係なく、覚悟を持って飛び込めば道は開けるということでやんす。26歳飲食未経験でも、2年で常連客に愛される存在になれるんでやんすから。」
ずん
「でもさ、26歳ってまだ若いし、やり直しもきくのだ。ボクみたいに...あ、ボクも若かったのだ!じゃあボクにもチャンスがあるのだ!」
ずん
「企業秘密なのだ!でもボクはまだまだ若いから、今から立ち食いそば屋を始めても遅くないのだ!『ずん蕎麦』絶対流行るのだ!」
やきう
「流行るわけないやろ。お前が作る蕎麦、誰が食うねん。」
でぇじょうぶ博士
「まあまあ、夢を持つのは悪いことじゃないでやんす。ただし、この若女将のように、朝5時起きで仕込みをする覚悟があるかどうかでやんすね。」
ずん
「...やっぱりボクは評論家になるのだ!立ち食いそば評論家なのだ!食べる専門なのだ!これなら朝7時半に起きなくていいのだ!」