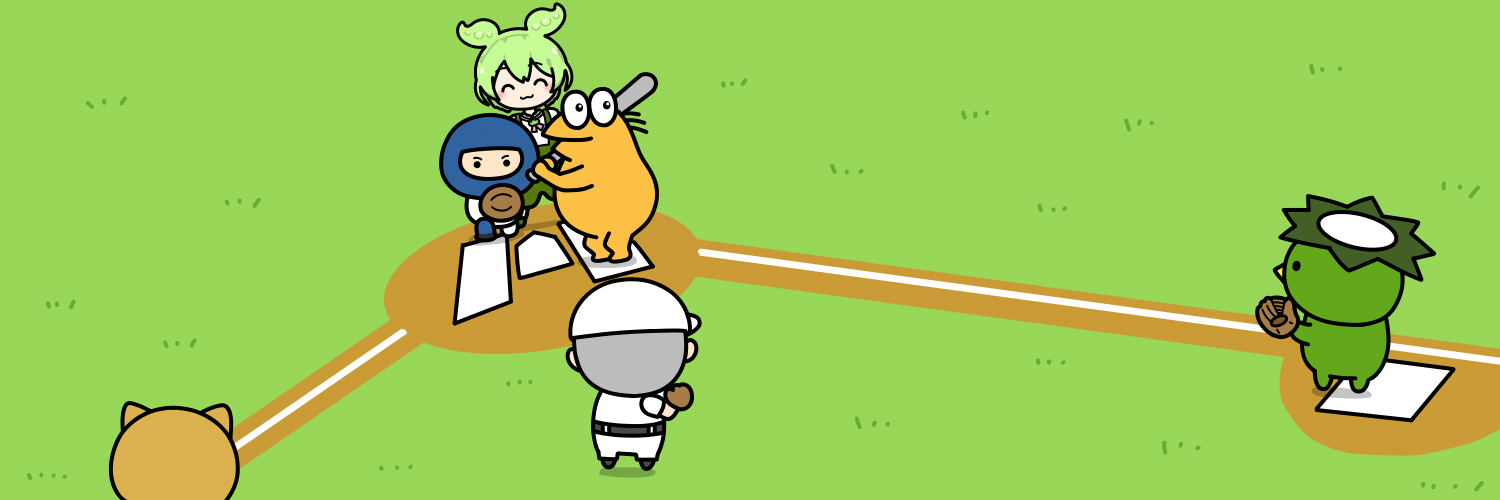ずん
「綿矢りささん、またなんか暗いの書いたらしいのだ。これってもしかして売れるための戦略なのだ?」
でぇじょうぶ博士
「むしろ逆でやんす。彼女は『書かないと考えをうまく進められない』と言っているでやんす。つまり、執筆という行為自体が思考のデバッグ作業になってるでやんすね。プログラマーがコード書きながら設計を考えるのと同じでやんす」
やきう
「はぁ?そんなん言い訳やろ。ワイかて毎日なんJに書き込んでるけど、思考なんか深まらへんで」
かっぱ
「そら君のは便所の落書きやからな。綿矢りささんは芥川賞作家やで」
ずん
「でも博士、主人公がネガティブすぎるって自分で言ってるのだ。読者ドン引きなんじゃないのだ?」
でぇじょうぶ博士
「そこが面白いところでやんす。彼女は『久乃が心の奥底へ潜り込んで考えてくれるほど、書いている私の気持ちまですっきりする』と言っているでやんす。これは心理学で言うところの『投影』と『カタルシス』でやんすね」
やきう
「要するに自分の闇を登場人物に押し付けて、スッキリしとるだけやんけ。これって一種のメンヘラムーブちゃうんか?」
かっぱ
「君よりマシやろ。君は押し付ける相手すらおらんやん」
でぇじょうぶ博士
「まあまあ。実は彼女の執筆スタイルは、哲学者のデカルトが言う『方法的懐疑』に近いものがあるでやんす。徹底的に内省することで、真理に到達しようとする試みでやんすね」
ずん
「うーん...でもさ、『愛されキャラじゃない』って書いてあるけど、そんな主人公の恋愛小説って需要あるのだ?」
やきう
「そらあるやろ。世の中、自分を『愛されキャラ』やと勘違いしとる痛い奴らばっかりやからな。現実見せたろってことや」
でぇじょうぶ博士
「実はですね、最近の恋愛小説市場では『完璧じゃない主人公』の方が共感を呼ぶというデータがあるでやんす。SNS時代の副作用で、みんな完璧を装うのに疲れているでやんすからね」
ずん
「なるほどなのだ...じゃあボクも小説書いて、内面のドロドロを吐き出せばスッキリするのだ?」
やきう
「お前の内面、ドロドロどころか空っぽやろ。書くことないやん」
かっぱ
「むしろ真っ白なキャンバスやと思えば、なんぼでも描けるで」
でぇじょうぶ博士
「ちなみに綿矢さんは『書くという習慣が自分にあってよかった』と語っているでやんす。これはおいらがコードを書くのと同じ感覚でやんすね。アウトプットすることで初めて、インプットが整理されるでやんす」
ずん
「でも博士、コード書いてもモテないって言ってたのだ。綿矢りささんは芥川賞作家でモテモテなのだ。全然違うじゃないのだ」
でぇじょうぶ博士
「...おいらは研究に集中するためにモテる必要はないと考えるでやんす」
やきう
「それ、ただの負け惜しみやん。ワイと同じレベルやな」
ずん
「ところで、この小説のタイトル『激しく煌めく短い命』って、なんか中二病っぽいのだ。博士、これって狙ってるのだ?」
でぇじょうぶ博士
「いい指摘でやんす。実はこのタイトルには、恋愛の儚さと情熱の両面を表現しようという意図があるでやんす。ワーズワースの詩『The Rainbow』の一節に通じるものがあるでやんすね」
やきう
「はいはい、また知識マウントか。お前ほんまウザいな」
かっぱ
「でも博士、『集大成的恋愛小説』って銘打ってるのは、ちょっとハードル上げすぎちゃうんか?」
でぇじょうぶ博士
「確かにでやんす。これは出版社のマーケティング戦略でやんすね。綿矢さん自身がそう言ったわけではないでやんすから。ただ、19歳で芥川賞を取った彼女が、今40歳前後で書く恋愛小説には、やはり特別な意味があるでやんす」
ずん
「へぇ...じゃあ、ボクが40歳になったら名作が書けるってことなのだ?」
やきう
「お前、40歳まで生き延びられると思っとるんか。その生活習慣で?」
ずん
「ひどいのだ!でも博士、『書かないと考えが進められない』って、逆に言えば頭の中だけじゃダメってことなのだ?」
でぇじょうぶ博士
「その通りでやんす。脳科学的に言えば、書くという行為は運動野と言語野を同時に刺激するので、思考が活性化されるでやんす。だからおいらも研究では、必ず手を動かしながら考えるでやんす」
かっぱ
「なるほどな。ワイも釣りしながら考え事するけど、似たようなもんか」
やきう
「釣りと執筆を一緒にすな。レベルが違いすぎるやろ」
でぇじょうぶ博士
「いやいや、それは偏見でやんす。『フロー状態』という観点から見れば、釣りも執筆も変わらないでやんす。要は没頭できるかどうかでやんす」
ずん
「じゃあボクもゲームしながら深く考えてるってことになるのだ!これは新発見なのだ!」
やきう
「お前がやってんのは『ウマ娘』のガチャやろ。思考もクソもあらへん」
かっぱ
「まあまあ。でも綿矢りささん、ネガティブな主人公書いてスッキリするって、なんか作家ってストレス発散方法が特殊やな」
でぇじょうぶ博士
「実は作家の多くがそういう傾向にあるでやんす。カフカもドストエフスキーも、自分の暗部を作品に投影することで精神のバランスを保っていたでやんす。いわば執筆は、彼らにとってのセラピーでやんすね」
ずん
「じゃあ、作家ってみんなメンヘラってことなのだ?」
やきう
「お前、今いいこと言ったかもしれんで。実際、名作書いた作家って、私生活めちゃくちゃなやつ多いやろ」
でぇじょうぶ博士
「むむむ、それは短絡的でやんす。メンヘラだから名作が書けるのではなく、深く内省する能力があるから名作が書けるでやんす。そしてその能力が、時として精神的な不安定さをもたらすだけでやんす」
ずん
「難しいのだ...でも、この記事読んで思ったんだけど、恋愛小説ってもう時代遅れなんじゃないのだ?みんなマッチングアプリで効率的に相手探してるのだ」
やきう
「それな。ワイもTinder入れとるけど、全然マッチせんわ。これもクソオスのせいやな」
かっぱ
「いや、それお前のプロフィール写真がアカンだけやろ」
でぇじょうぶ博士
「実は逆でやんす、ずん君。だからこそ恋愛小説に価値があるでやんす。効率化された現代の恋愛では味わえない、泥臭くて不器用な感情の揺れ動きを疑似体験できるでやんすからね」
ずん
「えぇー、でもボクは効率的な方がいいのだ。時間の無駄なのだ」
やきう
「お前、そもそも恋愛する相手おらんやろ。心配すな」
かっぱ
「もう君ら、恋愛の話になると途端にダメダメやな」
でぇじょうぶ博士
「まあ、綿矢さんの小説の真価は、そういう表面的な恋愛描写ではなく、人間の内面の複雑さを描くところにあるでやんす。特に今回は『小心で身勝手で偏狭』な主人公を容赦なく描いているでやんすからね」
でぇじょうぶ博士
「ちなみに、この『容赦ない書きっぷり』というのが、綿矢文学の真骨頂でやんす。読者に媚びず、登場人物の醜さまで正直に描く。これができる作家は少ないでやんす」
ずん
「でも博士、それって読んでて気分悪くならないのだ?ボクは気持ちいい話が読みたいのだ」
やきう
「お前、なろう系でも読んどけや。『異世界転生して無双する』とか、お前にぴったりやろ」
でぇじょうぶ博士
「それはそれで否定しないでやんす。ただ、綿矢さんの小説は『現実と向き合う』ためのものでやんすね。自分の中の醜い部分を認識することで、初めて成長できるという考え方でやんす」
ずん
「うーん...成長かぁ。ボク、もう十分成長してると思うんだけどなのだ」
ずん
「ひどいのだ!...でもさ、この小説、結局ハッピーエンドなのだ?」
でぇじょうぶ博士
「それはネタバレになるので言えないでやんすが、綿矢さんは『集大成的恋愛小説』と言っているでやんす。つまり、単純なハッピーエンドでもバッドエンドでもない、人生そのもののような結末が待っているはずでやんす」
やきう
「どうせ、『ふたりは別れたけど、それぞれの道を歩んでいく』みたいなオチやろ。ベタやん」
でぇじょうぶ博士
「むむむ、それは読んでみないとわからないでやんす。ただ、綿矢さんの過去作を見る限り、予想を裏切る展開が待っている可能性は高いでやんすね」
ずん
「じゃあボクも読んでみようかなのだ...って、何ページあるのだ?」
やきう
「お前、どうせ最後まで読まんやろ。積読確定やん」
かっぱ
「まあ、無理せんでええよ。君には絵本がお似合いや」
ずん
「もう!みんなしてボクをバカにするのだ!でも...やっぱり長い本は苦手なのだ...」