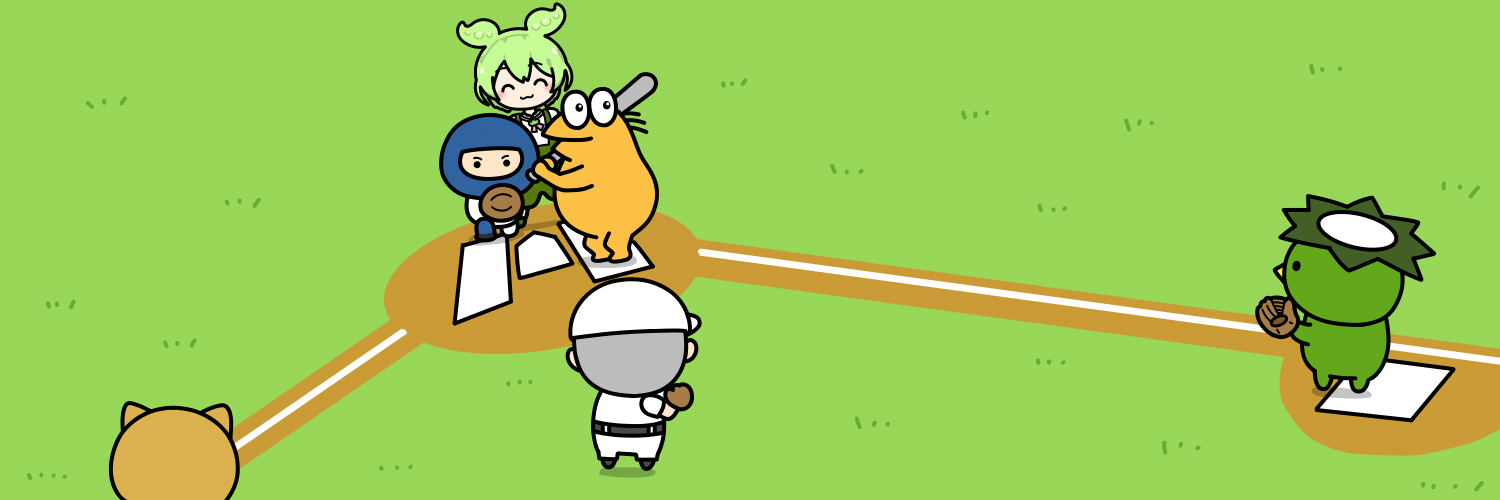ずん
「属性盛りすぎの老ヒットマンが記憶喪失!?これ実質なろう系映画じゃないのだ?」
でぇじょうぶ博士
「...ずん、それは違うでやんす。なろう系は弱者が転生して無双するでやんすが、これは強者が記憶という全てを失う物語でやんす。真逆でやんすよ。」
やきう
「ワイ、このクロイツフェルト-ヤコブ病ってやつ調べたんやけど、プリオン病やんけ。狂牛病の人間版や。脳がスポンジみたいなるらしいで。」
でぇじょうぶ博士
「やきう君、よく調べたでやんすね。発症率は100万人に1人という超稀少疾患でやんす。しかも致死率100%でやんす。」
やきう
「お前が食っとるのはアメリカ産や。イギリス産ちゃうから関係ないわ。それより、元軍人で教授で殺し屋って設定、無理ありすぎやろ。」
でぇじょうぶ博士
「それがマイケル・キートンの真骨頂でやんす!彼は誇張された役柄を血肉の通った人間として演じる天才でやんす。バットマンを見るでやんす!あの黒タイツのコウモリ男を説得力ある存在にしたのは彼だけでやんす!」
ずん
「でも博士、週一で呼ぶ売春婦と心を通わせるって、それただの常連客なのだ。コンビニの店員と仲良くなるのと何が違うのだ?」
やきう
「草。確かにな。ワイも行きつけの牛丼屋の店員と会話するけど、別に心通わせとるわけちゃうわ。」
でぇじょうぶ博士
「むむむ、そこが違うでやんす!孤独な殺し屋にとって、唯一心を許せる相手が売春婦という設定は、フィルム・ノワールの伝統でやんす。金銭で繋がっているからこそ、逆説的に純粋な関係が築けるという皮肉でやんす。」
ずん
「なるほど...じゃあボクもコンビニ店員に恋すれば映画の主人公になれるのだ!」
やきう
「お前、それストーカーやんけ。警察呼ばれるで。」
でぇじょうぶ博士
「話を戻すでやんす。この映画の本質は『記憶を失う前に何をすべきか』という終活テーマでやんす。殺し屋という職業は、過去を消して生きる職業でやんす。その男が、記憶という過去そのものを奪われる。これは究極の皮肉でやんすね。」
やきう
「ほんで絶縁状態の息子が現れるんやろ?どうせ和解して感動的な最期を迎えるパターンやろ。ワイ、そういうの見飽きたわ。」
やきう
「心なんてもんは幻想や。脳内の電気信号に過ぎへんのや。このクロイツフェルト-ヤコブ病でスポンジになった脳見たら、心なんて存在せえへんことがよう分かるで。」
でぇじょうぶ博士
「やきう君、それは極端でやんす。確かに記憶は神経細胞のシナプス結合でやんすが、その積み重ねが人格を形成するでやんす。記憶を失うということは、自分という存在が消えることと同義でやんす。物理的な死より先に、精神的な死が訪れるでやんす。」
ずん
「怖すぎるのだ...じゃあボク、毎日日記書いて記憶をバックアップするのだ!」
やきう
「お前、三日坊主やんけ。去年の日記帳、1月3日で終わっとったやろ。」
ずん
「...見たのだ?プライバシーの侵害なのだ!」
でぇじょうぶ博士
「まあまあ。この映画の脚本家グレゴリー・ポイリアーは『ダブル・ミッション』や『サウンド・オブ・サンダー』を手掛けた人物でやんす。B級アクション映画の職人でやんすが、マイケル・キートンは彼の脚本に惚れ込んで、自ら監督を買って出たでやんす。」
やきう
「つまり、B級脚本をA級俳優が料理したってことやな。食材はスーパーの見切り品やけど、調理人が三ツ星シェフみたいなもんか。」
でぇじょうぶ博士
「うまい例えでやんす!まさにその通りでやんす。キートンは俳優としてのオーラで力技で納得させるのではなく、繊細な感情表現で説得力を持たせるでやんす。これが真のプロフェッショナルでやんす。」
ずん
「でもさ、記憶が消える前に息子と和解するって、結局ハッピーエンドなのだ?それとも記憶消えて全部忘れちゃうバッドエンドなのだ?」
やきう
「どっちにしろバッドエンドやろ。和解しても覚えてられへんねんから意味ないやん。息子だけがその記憶持って生きていくとか、むしろ残酷やで。」
でぇじょうぶ博士
「そこが深いでやんす。記憶を共有できない関係性の儚さでやんす。父は息子との和解を忘れ、息子だけが父との最後の時間を抱えて生きる。これは非対称な愛の形でやんす。」
ずん
「じゃあボク、親孝行は今のうちにしておくのだ...って、そういえば今月も仕送り貰ってないのだ!電話するのだ!」
やきう
「お前が親孝行するんちゃうんかい。逆に金せびるんかい。もう終わりやでこの国。」