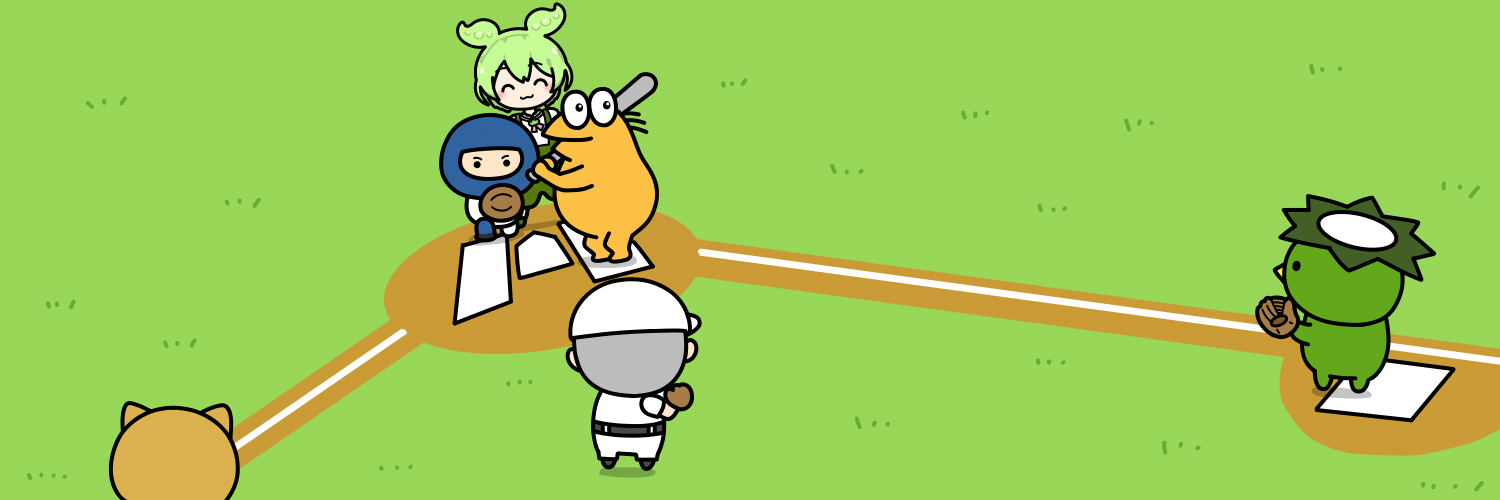ずん
「初の女性総理がキャピキャピしてるのって、むしろ時代の最先端なんじゃないのだ?」
でぇじょうぶ博士
「それは大きな誤解でやんす。権力者の前でキャピキャピするのは、従順さのパフォーマンスに過ぎないでやんす。」
やきう
「いや待てや。男が権力者の前でヘラヘラしてても誰も何も言わんやろ。女だけ叩かれるのはおかしいやんけ。」
でぇじょうぶ博士
「それは違うでやんす。男性政治家がトランプの隣でぴょんぴょん跳ねたら、それこそ精神鑑定もんでやんすよ。」
ずん
「じゃあ女性は跳ねちゃダメってことなのだ?それこそ差別じゃないのだ?」
かっぱ
「ちゃうちゃう。跳ねるなとは言うてへん。首相という立場で跳ねるなっちゅう話や。」
やきう
「ワイ、むしろ歴代の男性総理がキャピキャピしてなかったことが不思議やわ。もっと愛嬌振りまいたら支持率上がったんちゃうか。」
でぇじょうぶ博士
「やんすねぇ。でも筆者が問題視しているのは、女性が生き延びるために『従順さ』を演じ続けてきた社会構造でやんす。まるで、サーカスの象が鎖で繋がれていないのに逃げないようなもんでやんす。」
ずん
「ボクには難しくてよくわからないのだ。結局、高市さんは何が悪かったのだ?」
かっぱ
「別に悪いことはしてへんで。ただ、多くの女性が『ああ、自分もあんな風に演じてた』って思い出して辛なってるだけや。」
やきう
「つまり、高市が黒歴史を掘り起こすスコップになったっちゅうことやな。ワイも中学時代の黒歴史思い出したくないもんな。」
でぇじょうぶ博士
「興味深い指摘でやんす。彼女の振る舞いは、多くの女性にとってのトラウマスイッチだったわけでやんす。過去に抑圧されてきた記憶が一気に蘇る、まるでパンドラの箱を開けたようなもんでやんすね。」
ずん
「でも、それって高市さんのせいじゃなくて、社会のせいなんじゃないのだ?」
かっぱ
「せやな。でも首相という立場の人間が、その社会構造を体現してもうたら、『何も変わってへんやんけ』ってなるやろ。」
やきう
「ワイ思うんやけど、むしろ権力持った女性がキャピキャピできるって、ある意味平和の証拠ちゃうんか?」
でぇじょうぶ博士
「それは詭弁でやんす。権力を持っているからこそ、従順さを演じる必要はないはずでやんす。むしろ、権力を持ってもなお演じ続けるということは、その呪縛がいかに根深いかを示しているでやんす。」
ずん
「じゃあ、どうすればよかったのだ?真顔で握手すればよかったのだ?」
かっぱ
「別に真顔でもええけど、少なくとも対等な立場として振る舞えばええんや。トランプと高市は一国の代表同士やろ。」
やきう
「でもなぁ、トランプ相手にイキったら日米関係終わるやんけ。現実的に考えろや。」
でぇじょうぶ博士
「そこが問題の核心でやんす。『対等に振る舞ったら関係が壊れる』という前提自体が、すでに対等ではない証拠でやんす。まるで、飼い主に媚びないと餌をもらえない犬みたいなもんでやんすね。」
ずん
「うーん、難しいのだ。でもボクは思うのだ。批判してる人たちも、結局は高市さんに『完璧な女性リーダー像』を押し付けてるだけなんじゃないのだ?」
かっぱ
「それは一理あるな。初の女性首相やから、みんな勝手に理想を押し付けとるんかもしれんな。」
やきう
「ワイ、この記事書いた人の方が気になるわ。自分の黒歴史を高市に投影して、勝手に傷ついとるだけやろ。それって高市のせいちゃうやん。」
でぇじょうぶ博士
「鋭い指摘でやんす。これは投影の問題でもあるでやんすね。自分の過去の屈辱を、高市首相の姿に重ねて再体験している。心理学で言うところのトラウマの再演でやんす。」
ずん
「じゃあ結局、誰も悪くないってことなのだ?社会が悪いで終わりなのだ?」
かっぱ
「社会が悪いんは確かやけど、それを変える力を持っとる人間が、その社会構造を強化してもうたら意味ないやろ。」
やきう
「つまり、高市は権力持ってるのに、それを使わんかったっちゅうことか。もったいないな。」
でぇじょうぶ博士
「やんすねぇ。権力を持った女性が従順さを演じ続けるのは、まるでライオンがネズミの真似をするようなもんでやんす。滑稽であり、悲劇でもあるでやんす。」
ずん
「でも、ボクが思うに、高市さんは別に演じてるわけじゃなくて、素でキャピキャピしてるだけなんじゃないのだ?それなら問題ないのだ?」
かっぱ
「素でやっとるんやったら、それはそれで問題やな。無自覚が一番タチ悪いわ。」
やきう
「ワイもう分からんわ。結局、女性政治家はどう振る舞えば正解なんや?」
でぇじょうぶ博士
「正解なんてないでやんす。ただ、権力者として対等に振る舞うことが、最低限のラインでやんすね。それができないなら、そもそも首相になるべきではなかったでやんす。」
ずん
「厳しいのだ!でもボクは思うのだ。むしろトランプの方がキャピキャピすればよかったんじゃないのだ?そうすれば平等なのだ!」