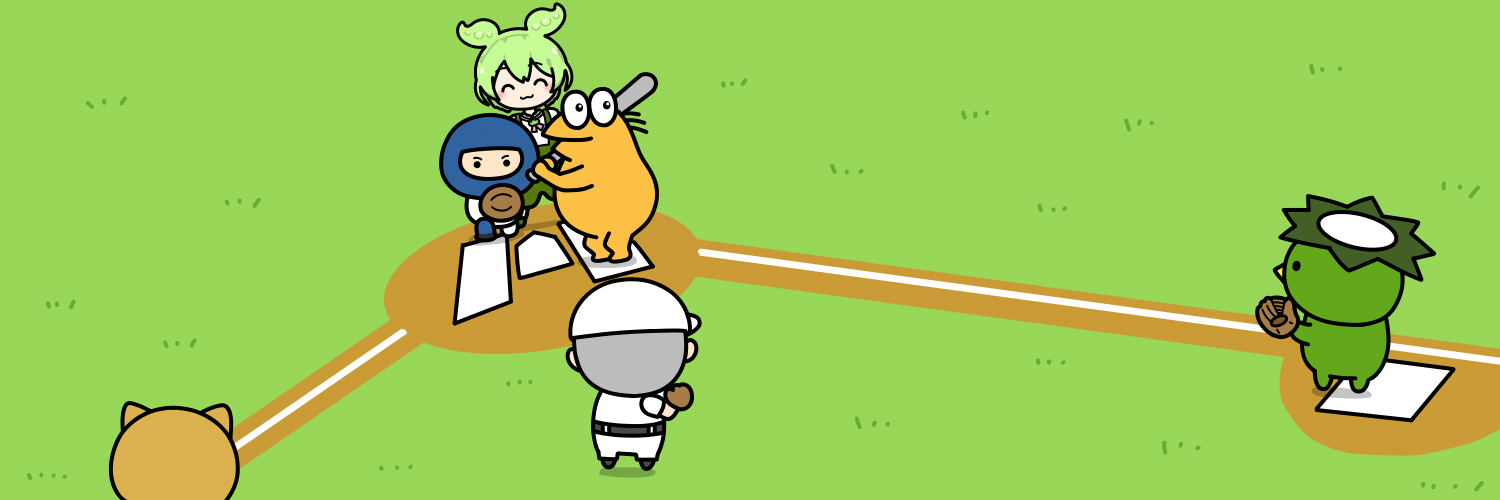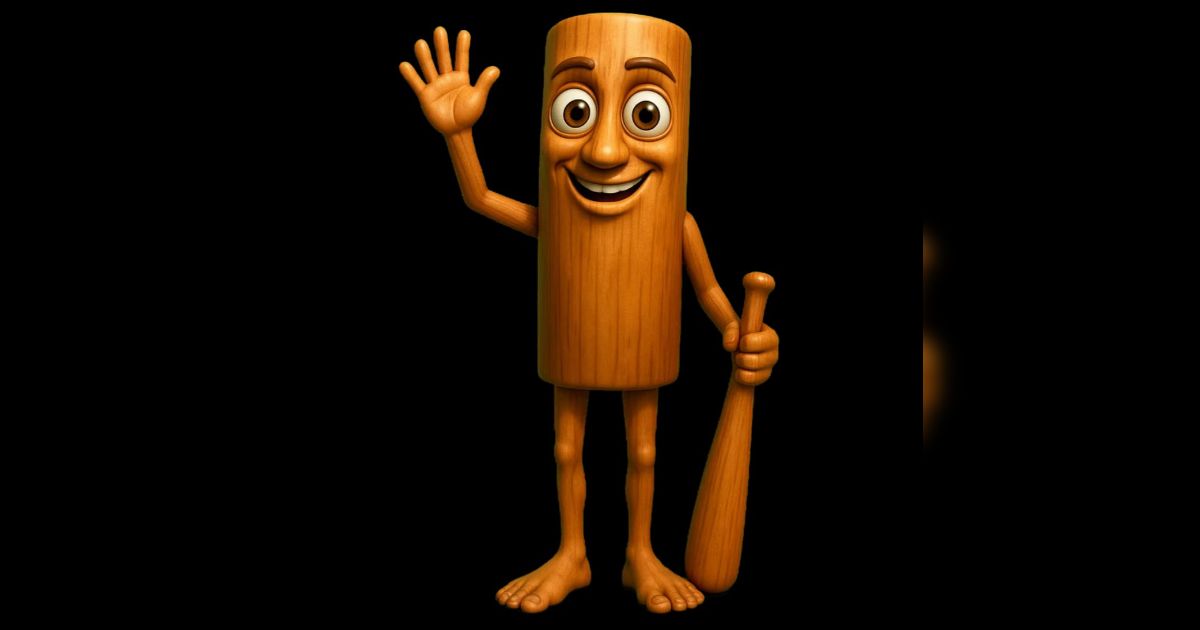ずん
「なんかもうボク、時代についていけないのだ。AIが作った謎のキャラが子供に流行ってるって、意味わかんないのだ!」
やきう
「ワイも初耳やで。つーか、トゥントゥントゥンサフールって何や。お経か?」
でぇじょうぶ博士
「やれやれ、これは現代のデジタルネイティブ世代ならではの現象でやんすね。イタリアンブレインロット、通称イタブレと呼ばれる生成AIキャラクターでやんす。」
かっぱ
「何がイタリアやねん。パスタでも食っとけや。」
ずん
「でもこれ、親が全然知らないってヤバくないのだ?情報格差がエグいのだ!」
でぇじょうぶ博士
「まさにその通りでやんす。TikTokとYouTubeを主戦場に、AIが自動生成したキャラが1000種類以上存在し、イタリア語の人工音声で紹介されるという、まるでシュールレアリスムの悪夢のような世界観でやんすよ。」
やきう
「イタリア語で喋る謎キャラとか、もはやホラーやろ。子供の教育に悪いんちゃうか。」
かっぱ
「お前が言うな。ニートのくせに教育語るとか、100年早いわ。」
ずん
「でもさ、これって結局AIが作った適当なキャラってことでしょ?なんで子供たちはそんなのにハマるのだ?」
でぇじょうぶ博士
「それこそが現代の子供文化の核心でやんすね。彼らにとっては『誰が作ったか』より『面白いかどうか』が全てでやんす。しかもロブロックスというゲームにも登場し、Tシャツまで売られてる。完全に一大ムーブメントでやんすよ。」
やきう
「つまり、ワイらおっさんが知らん間に、子供経済圏が別次元で回っとるってことか。恐ろしいわ。」
かっぱ
「お前、家から出てへんのに経済語るんか。せめて働いてから言えや。」
ずん
「でも博士、これって親からしたら不安じゃないのだ?何見てるかわからないって怖いのだ!」
でぇじょうぶ博士
「それは正論でやんす。しかし考えてみてくだされ。おいらたちが子供の頃だって、親は『たまごっち』や『ポケモン』の何が面白いのか理解できなかったはずでやんす。世代間ギャップは永遠のテーマでやんすよ。」
やきう
「確かにな。でも今回のは、AIが勝手に量産しとるキャラやろ?クオリティもバラバラやし、得体が知れんわ。」
かっぱ
「お前の人生の方が得体知れんわ。履歴書の空白期間、どないなっとんねん。」
ずん
「じゃあボクもイタブレのTシャツ買って、子供に擦り寄ろうかなと思うのだ!」
でぇじょうぶ博士
「それは悪手でやんす。大人が理解しようと必死になればなるほど、子供たちは次の流行に移っていくでやんすよ。まるで蜃気楼を追いかけるようなもんでやんす。」
やきう
「じゃあどうすればええんや。完全に置いてけぼりやんけ。」
でぇじょうぶ博士
「答えは簡単でやんす。子供に『それ何?教えて』と素直に聞けばいいでやんす。小児科医が『医者のくせに知らんのか』と言われたエピソードがありましたが、これこそが理想的な関係性でやんすよ。子供が優位に立てる話題があることは、彼らの自尊心を育むでやんす。」
かっぱ
「なるほどな。つまり、知らんことは恥やなくて、コミュニケーションのネタってことか。」
ずん
「でもさ、AIが勝手に作ったキャラが流行るって、将来的にヤバくないのだ?人間が作ったコンテンツが負けちゃうのだ!」
でぇじょうぶ博士
「鋭い指摘でやんす。実際、これは文化の転換点かもしれないでやんすね。今後、AIが生成したコンテンツと人間が作ったコンテンツの境界が曖昧になっていく可能性は高いでやんす。」
やきう
「結局、子供たちは面白ければ何でもええんやな。制作者とか関係あらへん。」
かっぱ
「お前も面白くないから誰にも相手されてへんやろ。鏡見てから喋れや。」
ずん
「じゃあボク、今から『ブンブンブンバフール』ってキャラ作って一攫千金狙うのだ!」
でぇじょうぶ博士
「それは無理でやんす。既に1000種類以上あるでやんすから、今さら参入しても埋もれるだけでやんすよ。」
やきう
「しかも、お前のセンスやとコケること間違いなしやで。ネーミングからしてダサいわ。」
かっぱ
「つーか、お前仕事せえや。エリート会社員って設定どこいったんや。」
ずん
「むむむ...じゃあボクは、子供たちに『おじさんもトゥントゥン知ってるよ!』って言って好かれる作戦でいくのだ!」
でぇじょうぶ博士
「それは最悪の一手でやんす。子供たちにとって、大人が知ってる時点でそのコンテンツは『終わった』も同然でやんすよ。まるで、親がLINEを使い始めた途端に若者がInstagramに移行したのと同じでやんす。」
やきう
「つまり、大人が理解した瞬間に価値が消えるってことか。子供文化、残酷すぎやろ。」
かっぱ
「まあ、お前は何も理解してへんから安心せえや。永遠に価値ゼロや。」
ずん
「じゃあもうボク、トゥントゥンのこと考えるのやめて、昼寝するのだ!現代っ子の文化についていけないのは、大人の特権なのだ!...多分なのだ。」