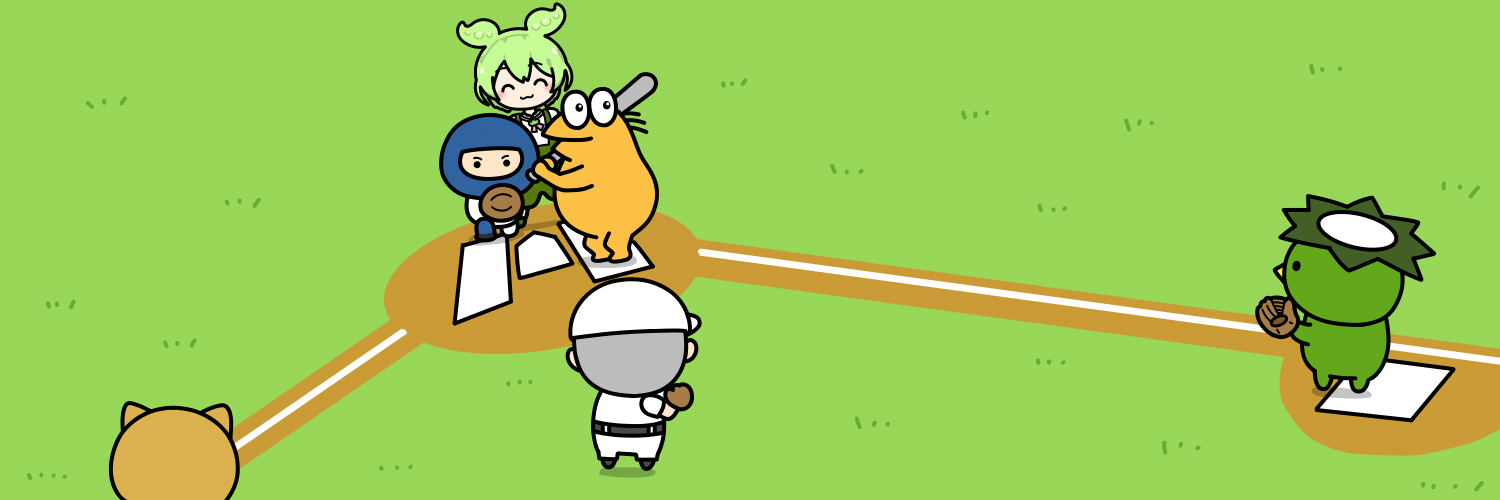ずん
「安西ひろこさんが突発性難聴って聞いたけど、これって治るものなのだ?」
でぇじょうぶ博士
「うーん、それがまた厄介な病気でやんすね。突発性難聴は、まるで突然電源が落ちるパソコンみたいに、ある日突然耳が聞こえなくなる病気でやんす。原因不明で、治療しても完全回復する人もいれば、しない人もいるでやんす。」
やきう
「要するに運ゲーってことやろ?医者も結局わからんのやったら、ワイらと変わらんやんけ。」
ずん
「えぇ…じゃあ、ボクもいつなるかわからないってことなのだ?」
でぇじょうぶ博士
「その通りでやんす。ストレス、睡眠不足、過労…全部リスク要因でやんすね。特に40代以降に多いでやんすから、安西さんの年齢も関係してるかもしれないでやんす。」
やきう
「ステロイドが効かん5%に入ったんか?これは地獄やな。高気圧酸素治療とか、金かかりそうやし。」
ずん
「高気圧酸素治療って何なのだ?潜水艦にでも入るのだ?」
でぇじょうぶ博士
「まあ、近いでやんすね。専用のカプセルに入って、高濃度の酸素を吸うんでやんす。血流を良くして、耳の神経を回復させる狙いでやんす。でも効果は人それぞれで、まるでガチャを引くようなもんでやんす。」
やきう
「結局ギャンブルやんけ。金だけ取られて治らん可能性もあるってことやろ?医療ってホンマにえげつないわ。」
でぇじょうぶ博士
「それは逆効果でやんす。耳を使わないと、聴力が衰えるでやんすよ。むしろ、適度に音楽を聴いたり、会話したりするのが大事でやんす。」
やきう
「ワイみたいに引きこもって、誰とも話さんかったらアカンってことか?」
ずん
「やきうさん、それって元から耳悪いんじゃないのだ?」
やきう
「うるさいわ。ワイは選んで無視しとるだけや。」
でぇじょうぶ博士
「まあ、安西さんは仕事を続けるって言ってるでやんすから、精神的には強いでやんすね。でも、片耳が聞こえないってのは、日常生活でかなりのハンデでやんす。距離感がつかめなかったり、会話が聞き取りにくかったり…まるで常に片方のイヤホンが壊れてるようなもんでやんす。」
やきう
「芸能界で仕事続けるんやったら、相当キツイやろな。撮影現場とか、音響も大事やし。」
ずん
「でも、ボクだったらこれを理由に休むのだ。だって、耳が聞こえないって最高の言い訳じゃないのだ?」
でぇじょうぶ博士
「ずん、それは不謹慎でやんす…。でも、確かに芸能人は体が資本でやんすから、こういう病気は致命的でやんすね。特に音楽番組とかバラエティとかは、タイミングが命でやんすから。」
やきう
「ワイの予想やけど、これから突発性難聴になる芸能人、もっと増えるで。過労とストレスまみれの業界やからな。」
ずん
「じゃあ、芸能界自体がブラック企業みたいなものなのだ?」
でぇじょうぶ博士
「ある意味そうでやんすね。華やかに見えて、裏では過酷な労働環境でやんす。安西さんも、まだ46歳でやんすから、これからどう回復していくかが注目でやんす。」
やきう
「まあ、治らんかったら引退やろな。厳しいけど、それが現実や。」
ずん
「むぅ…じゃあ、ボクは今のうちに耳を大事にするのだ!大音量で音楽聴くのやめるのだ!」
でぇじょうぶ博士
「それは正解でやんす。イヤホンの音量は、周りの音が少し聞こえるくらいが理想でやんす。あと、長時間の使用も避けるべきでやんす。」
やきう
「ワイは最初から静かに暮らしとるから問題ないわ。むしろ、耳が良すぎて隣の家の夫婦喧嘩まで聞こえるんや。」
でぇじょうぶ博士
「まあ、安西さんには一日も早く回復してほしいでやんすね。でも、突発性難聴は早期治療が肝心でやんすから、もしもの時は速攻で病院に行くべきでやんす。」
ずん
「なるほどなのだ…でも、ボク病院嫌いなのだ。待ち時間長いし、注射痛いし…」
やきう
「お前、ガキか。注射怖がっとる場合やないやろ。」
ずん
「だって、注射って無駄に痛くないのだ?あれ絶対わざとやってるのだ!」
でぇじょうぶ博士
「ずん、それはただの被害妄想でやんす…。でも、確かに医療現場も忙しいでやんすから、多少雑になることもあるかもしれないでやんすね。」
やきう
「ワイの予想やけど、これから芸能人の病気公表、もっと増えるで。SNSで発信しやすくなったからな。昔やったら隠してたようなことも、今は全部オープンや。」
ずん
「じゃあ、ボクも何か病気になったら公表するのだ!そしたら同情されて、仕事休めるのだ!」
でぇじょうぶ博士
「ずん、それは不純な動機でやんす…。でも、確かに病気を公表することで、同じ悩みを持つ人が勇気づけられることもあるでやんす。安西さんの公表も、そういう意味では意義があるでやんすね。」
やきう
「まあ、ワイはどっちでもええわ。ただ、治らんかったら可哀想やなとは思うで。」
ずん
「やきうさん、たまにはいいこと言うのだ!でも、ボクはやっぱり病気にならないように、今日からずっと寝て過ごすのだ!」