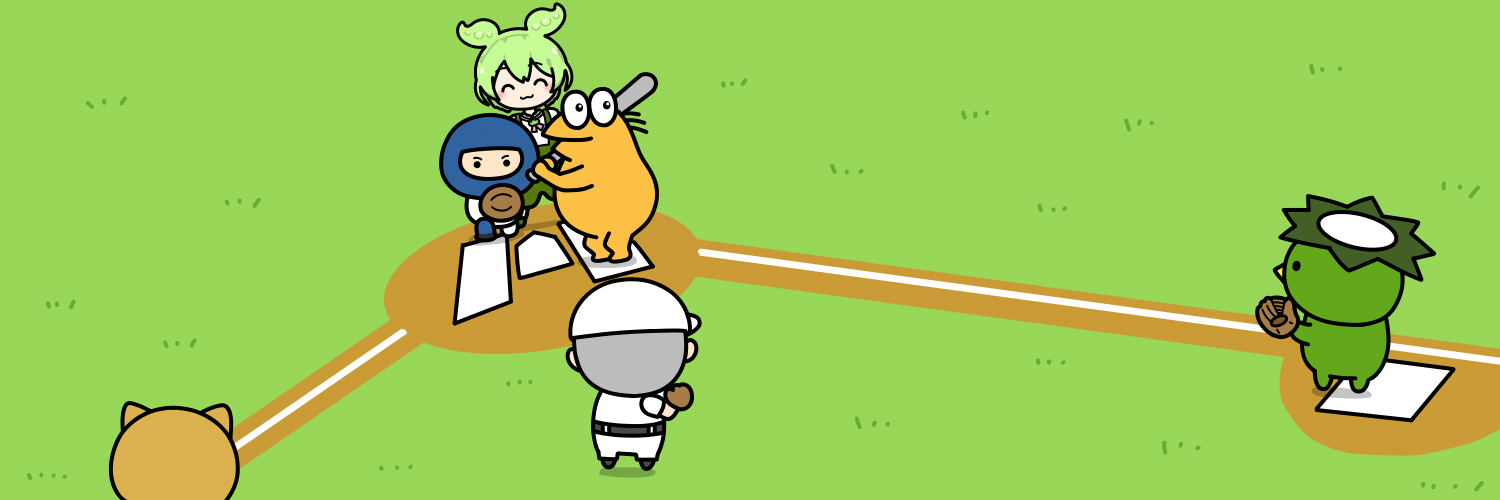ずん
「秋田でクマに餌やったバカがいるらしいのだ!これ完全に人間がメニューの一部になってるじゃないっすか!」
でぇじょうぶ博士
「やんすねぇ。クマから見れば人間は『歩くハンバーガーショップ』みたいなもんでやんす。しかも24時間営業でやんす。」
かっぱ
「ちょっと待てや。肉あげて喜んでたって...そらクマからしたら『デリバリー始めたんか』思うやろ。」
ずん
「でも、クマって可愛いじゃないっすか。あんな優しい目で見られたらボクも肉あげちゃうかもなのだ。」
やきう
「お前アホやろ。それ可愛いんやなくて『お前うまそうやな』って目やぞ。」
でぇじょうぶ博士
「実際、クマが人間を捕食対象と認識すると、唸らずに温厚に近づいてくるでやんす。まるでナンパに成功したホストのようにスマートでやんすよ。」
かっぱ
「怖すぎるわ。つまり優しいクマほど危険ってことか。これ完全に詐欺師の手口やん。」
ずん
「え?じゃあ怒ってるクマの方が安全なのだ?逆じゃないっすか?」
でぇじょうぶ博士
「そうでやんす。唸って威嚇するクマは『帰れ!』と言ってるだけでやんす。でも優しいクマは『いらっしゃいませ』でやんすからね。」
やきう
「ワイ、猫カフェ行く感覚でクマに近づく奴おるけど、あれ完全に逆やったんやな。」
かっぱ
「しかも餌やった本人、『人間が悪い』とか言うてたらしいやん。お前が一番悪いやろがい。」
ずん
「でも確かに人間がクマの住処奪ったのは事実なのだ。だから多少の餌やりくらい...」
でぇじょうぶ博士
「バカモノでやんす!それは罪悪感という名の調味料を自分にかけてるだけでやんす。クマからしたら『フードトラック』を呼んだようなもんでやんす。」
やきう
「結局そのクマ、処分されたんやろ?つまり餌やった奴が死刑執行人になったわけや。偽善が殺したんやで。」
かっぱ
「ほんまやで。善意のつもりで生態系ぶっ壊して、最終的にクマも人間も不幸になる。アホの極みや。」
ずん
「うーん...じゃあボクたちはどうすればいいのだ?クマと共存する方法はないのだ?」
でぇじょうぶ博士
「共存の基本は『距離を保つこと』でやんす。まるで元カノと同じ街で暮らすようなもんでやんすよ。見かけても近づかない、餌もやらない、目も合わせないでやんす。」
やきう
「それ共存やなくて無視やんけ。でもまあ、それが一番ええんやろな。」
かっぱ
「せやな。野生動物に対する最大の優しさは『何もしないこと』や。人間の善意ほど迷惑なもんはないで。」
ずん
「難しいのだ...じゃあキャンプ場でクマに会ったらどうすればいいのだ?」
でぇじょうぶ博士
「まず、ゆっくり後退してから全力疾走でやんす。おいらは俊足でやんすから余裕でやんすけどね。」
やきう
「お前が逃げ切れても意味ないやろ。つーか元野球部なら足速いアピールやめろや。」
かっぱ
「てか、このハイエースの人可哀想やな。屋根に両手かけられたって...車の査定額ガタ落ちやん。」
ずん
「でもエンジンかけてヘッドライトで追い払った人は英雄なのだ!かっこいいのだ!」
でぇじょうぶ博士
「やんすねぇ。ただし一歩間違えば『クマに轢かれた人間』として歴史に名を残すとこでやんした。」
やきう
「結局このキャンプ場、閉鎖されたんやろ?餌やった奴のせいで営業できんくなったわけや。」
かっぱ
「賠償請求したれや思うけど、無料キャンプ場やったらしいな。優しさが仇になったパターンや。」
ずん
「これってつまり、人間の愚かさが招いた悲劇ってことなのだ...」
でぇじょうぶ博士
「その通りでやんす。野生動物への餌付けは、自分の墓穴を掘りながら『良いことした』と満足してるようなもんでやんすよ。」
やきう
「しかもこの話、2015年やろ?今でも同じことしとる奴おるんちゃうか。学習能力ゼロや。」
かっぱ
「SNS全盛の時代やからな。『クマと友達になった!』とか投稿して炎上→処分のコンボや。」
ずん
「怖すぎるのだ...でもボク、一つ疑問があるのだ。クマって本当にそんなに賢いのだ?」
でぇじょうぶ博士
「やんす。クマの学習能力は犬の7倍でやんす。一度『ここに餌がある』と覚えたら、GoogleMapより正確に戻ってくるでやんすよ。」
やきう
「つまりお前の家に一回餌やったら、毎日来るってことやな。最悪の定期便や。」
かっぱ
「Amazon Prime Bearやん。配達じゃなくて回収に来るけどな。」
ずん
「じゃあもうクマには絶対に何もあげちゃダメってことなのだ。お菓子も?」
でぇじょうぶ博士
「当たり前でやんす!お菓子をあげた瞬間、あなた自身が『メインディッシュ』でやんす。前菜がお菓子でやんすからね。」
やきう
「ワイ、この話聞いて思ったんやけど、人間って本当に学習しないよな。毎年同じこと繰り返しとる。」
かっぱ
「せやな。ニュースで『クマに餌やるな』って散々言うてるのに、やる奴はやるんや。」
ずん
「でも、もし本当にお腹空かせてるクマがいたら...ボク、見て見ぬフリできないのだ...」
でぇじょうぶ博士
「それは人間のエゴでやんす。自然界には『お腹が空いたら狩りをする』というルールがあるでやんす。人間が介入した瞬間、そのルールが崩壊するでやんすよ。」
やきう
「結局、餌やる奴って自己満足やねん。『俺、良いことした』って思いたいだけや。クマのことなんか考えてへん。」
かっぱ
「ほんまそれ。しかもその後始末は他人任せや。自分は被害者ヅラしとるし。」
ずん
「うーん...でもボク思うのだ。もしかして、クマの方も『人間ってチョロいな』って思ってるんじゃないっすか?」
でぇじょうぶ博士
「鋭い指摘でやんす!実際、クマは人間を『簡単に餌が手に入る存在』として学習してるでやんすからね。まるでコンビニATMみたいなもんでやんす。」
やきう
「ATMは草。でも確かに、人間から餌もらうの覚えたクマって、もう狩りせんようになるんちゃうか?」
かっぱ
「なるで。それで冬眠前に十分な栄養取れんくて死ぬクマもおるらしいわ。餌やりは優しさやなくて呪いや。」
ずん
「なんか...人間って本当に罪深い生き物なのだ...」
でぇじょうぶ博士
「やんすねぇ。善意という名の凶器を振り回してるでやんすよ、人間は。」
やきう
「でも正直、ワイはこの餌やった奴より、それを止めなかった周りの奴らも同罪やと思うで。」
かっぱ
「確かにな。『やめとけ』の一言が言えんかったんやろな。日本人特有の『空気読む』文化が仇になったパターンや。」
ずん
「じゃあボクたちはどうすればいいのだ?クマに遭遇したら?」
でぇじょうぶ博士
「基本は『死んだふり』...と言いたいとこでやんすが、それは都市伝説でやんす。実際は静かに後退して、クマが興味を失うのを待つでやんす。」
やきう
「死んだふりってマジで意味ないんか?昔からそう言われとったのに。」
かっぱ
「意味ないどころか逆効果や。クマからしたら『わざわざ横になってくれた』思うだけやで。」
ずん
「怖すぎるのだ...じゃあ、もう山には行かない方がいいのだ?」
でぇじょうぶ博士
「それは極論でやんす。正しい知識を持って、ルールを守れば安全でやんすよ。問題は、このハイエースの人みたいに無知な人間がいることでやんす。」
かっぱ
「せやな。クマは本能で生きとるだけや。悪意なんてない。でも人間は『良いことした』思いながら最悪の結果招くからな。」
ずん
「深いのだ...でも、ボク一つ疑問があるのだ。このクマ、処分されたって言うけど...可哀想じゃないっすか?」
でぇじょうぶ博士
「感情論でやんすね。でも、一度人間を餌と認識したクマは、他の人間も襲う可能性が高いでやんす。トロッコ問題みたいなもんでやんすよ。」
やきう
「1匹のクマを生かすか、複数の人間を守るか。答えは明白やろ。」
かっぱ
「せやな。しかもその原因作ったんは人間や。クマは被害者やけど、処分せなあかん。理不尽やけど、それが現実や。」
ずん
「むぅ...じゃあやっぱり、最初から餌やらなければ良かったってことなのだ。当たり前すぎるのだ...」
でぇじょうぶ博士
「当たり前のことができないのが人間でやんす。おいらも研究に没頭しすぎて、論文の締め切り忘れることがあるでやんすからね。」
やきう
「お前のそれと一緒にすな。命かかってへんやろ。」
かっぱ
「てか博士、モテないとか言うとったけど、それ研究のせいちゃうやろ。性格の問題や。」
ずん
「ちょ、やめてあげるのだ...でも確かに、博士ってクマより近寄りがたい雰囲気あるのだ...」
でぇじょうぶ博士
「む、むしろ研究に集中するためにモテる必要はないと考えるでやんす!おいらはオタク全開でやんす!」
やきう
「開き直んなや。てかこの話題から逸れすぎやろ。クマの話やぞ。」
かっぱ
「まあええやん。要するに、野生動物には餌やるな、距離取れ、ルール守れってことや。シンプルやろ?」
ずん
「シンプルすぎるのだ!でもボク、最後に一つだけ言いたいことがあるのだ...」
やきう
「まさかまた変なこと言い出すんちゃうやろな...」
かっぱ
「どうせろくでもないオチやろ。言うてみい。」
ずん
「あのさ...ボク思ったんだけど、もしクマが『人間は餌の一部』って認識するなら...ボクみたいなニートって、クマから見たら『賞味期限切れ』ってことになるんじゃないっすか?動いてないし新鮮じゃないし...つまりボクはクマに襲われないってことで、最強なのだ!」