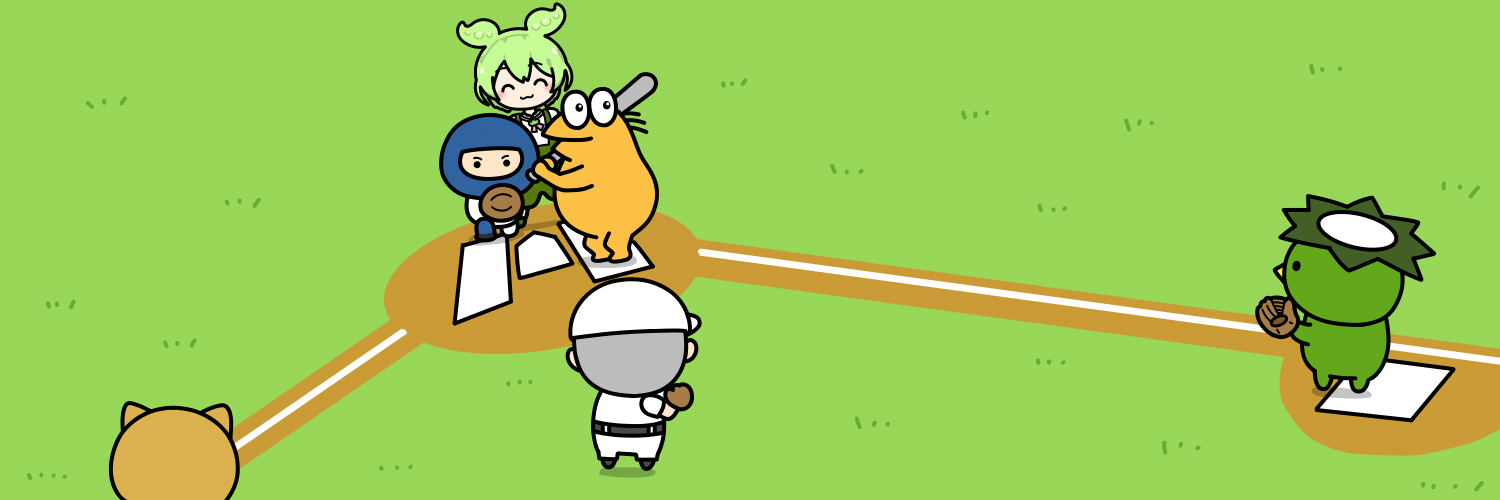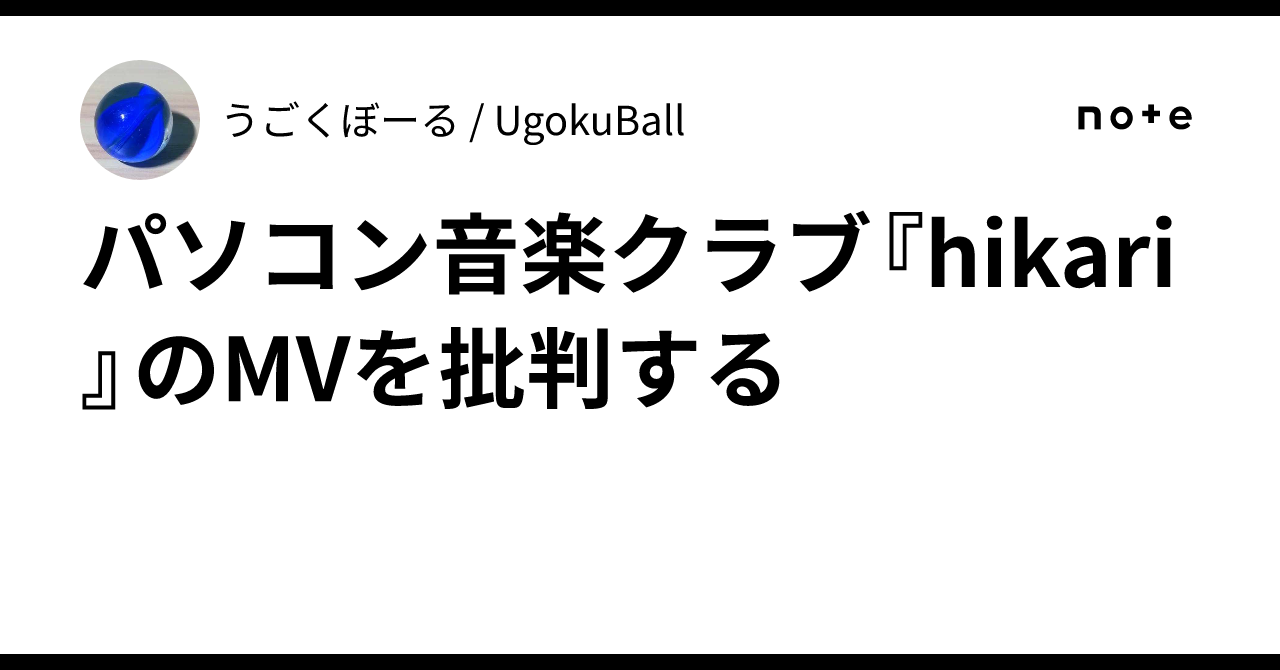ずん
「AIが音楽に合わせられないって、それ致命的じゃないのだ?」
でぇじょうぶ博士
「まさにそこが問題の核心でやんす。映像と音楽のズレは、カラオケで一拍遅れて歌う酔っ払いみたいなもんでやんすよ。」
かっぱ
「せやな。イントロのコップがピアノのリフに合ってへんって、それもう根本的にあかんやん。」
ずん
「でも、制作者は『音楽に合わせて映像が動く気持ちよさを重視した』って言ってるのだ。これは詐欺なのだ!」
やきう
「草。重視したけど実現できてへんのやったら、それただの願望やんけ。」
でぇじょうぶ博士
「むむむ、しかし16分音符のズレを人間が感じ取れるというのは、音楽の持つ精密性の証明でもあるでやんす。」
かっぱ
「そんな高尚な話ちゃうやろ。単純に調整不足や。1:08のコップがぶつかるタイミング、明らかに早いって書いてあるやん。」
やきう
「音痴っていうか、耳が腐っとるんやろな。ワイのカーチャンのがまだマシなタイミングで料理出すで。」
でぇじょうぶ博士
「しかし、サビ直前のスローモーションからの展開は評価されているでやんす。つまり、全てがダメというわけではないでやんすね。」
かっぱ
「そら部分的に当たっとるところもあるやろうけど、トータルで見たら赤点やん。」
やきう
「失敗っていうより、半端もんやな。AIの可能性を見せたかったんやろうけど、逆に限界を露呈しとるわ。」
でぇじょうぶ博士
「興味深いのは、制作者が『AIは人の個性を強調する』と言っている点でやんす。確かに、この不完全さこそが平牧監督の『個性』なのかもしれないでやんすが...」
かっぱ
「それ、ただの言い訳やん。個性言うたら何でも許されるんかいな。」
ずん
「でも、6年越しのMV公開でこれって、ファンはがっかりなのだ。」
やきう
「せやな。6年待たせてコップがピョンピョン跳ねるだけとか、ワイやったら発狂しとるで。」
でぇじょうぶ博士
「ただ、YouTubeのコメント欄では称賛の声も多いと記事にあるでやんす。生成AI懐疑派と推進派の対立が見え隠れするでやんすね。」
かっぱ
「そんなん関係あらへん。音楽と映像が合ってへんっちゅう技術的な問題やろ。AI云々の前に、基本ができてへんのや。」
ずん
「じゃあ、人間が作った方が良かったってことなのだ?」
やきう
「当たり前やろ。少なくとも人間やったら、音符スキップするとか、8分音符分早くなるとかせえへんわ。」
でぇじょうぶ博士
「しかし、これは過渡期の作品として記録されるかもしれないでやんす。まるで初期の無声映画が今見ると稚拙に見えるように、でやんす。」
かっぱ
「過渡期って言うたら聞こえはええけど、要は未熟やろ。プロの仕事とは言えへんわ。」
ずん
「でも、『AIらしい不気味さ』を生かしてるって評価もあるのだ。」
やきう
「不気味さ生かすんやったら、ホラー映画でも撮っとけや。パソコン音楽クラブの爽やかな曲に不気味さいらんやろ。」
でぇじょうぶ博士
「むむむ、やはり『どの音を拾っているのか不明瞭』という指摘が致命的でやんすね。視聴者は混乱するばかりでやんす。」
かっぱ
「そらそうや。音楽MVの基本は『音と映像のシンクロ』やろ。それができてへんのやったら、ただのスライドショーと変わらんがな。」
ずん
「つまり、このMVは『技術デモ』としては面白いけど、『作品』としては微妙ってことなのだ?」
やきう
「ええこと言うやん、ずん。まさにそれや。Googleの宣伝動画としては及第点やけど、アートとしては不合格や。」
でぇじょうぶ博士
「しかし、2つのコップに主題を絞った『切り詰められた構成』というのは、むしろAIの限界を正直に表現しているとも言えるでやんす。」
かっぱ
「限界を表現するんやのうて、限界を超えるんがアーティストの仕事やろ。それができてへんから批判されとるんやで。」
ずん
「じゃあ、今後AIがもっと進化したら、こういう問題は解決されるのだ?」
やきう
「解決されるかもしれへんけど、そしたら結局人間が作るんと変わらんようになるんちゃうか。それやったら最初から人間が作った方が早いやん。」
でぇじょうぶ博士
「興味深い逆説でやんすね。AIが完璧になればなるほど、AIを使う意味が失われていくという...まるで自己矛盾の塊でやんす。」
かっぱ
「ほんま哲学的なこと言い出したな。そんなん考えとる暇あったら、ちゃんとリズム合わせる方法考えろや。」
ずん
「でも、筆者は『何度も見るうちに好きなところも出てきた』って言ってるのだ。つまり、慣れの問題なのだ?」
やきう
「それ、ストックホルム症候群みたいなもんやろ。何度も見せられたら、脳が勝手に良い部分を探し出すんや。」
でぇじょうぶ博士
「しかし、その『慣れ』というのも重要な要素でやんす。新しい表現は常に違和感から始まるでやんすからね。」
かっぱ
「新しい表現と手抜きは違うで。これは明らかに調整不足や。新しさで誤魔化したらあかん。」
やきう
「一番の問題は『音楽に合わせて映像が動く気持ちよさを重視した』って言いながら、実際には全然合ってへんことやろ。有言不実行や。」
でぇじょうぶ博士
「つまり、制作者の意図と結果のギャップが大きすぎるということでやんすね。まるで『美味しいラーメンを作る』と言いながら、カップ麺を出されたような感じでやんす。」
かっぱ
「せやな。しかもそのカップ麺、お湯の量間違えとるような状態やで。」
ずん
「でも、コメント欄で称賛してる人たちは何を見てるのだ?」
やきう
「そら、AIすげえええええって騒いどるだけやろ。中身ちゃんと見てへんのや。」
でぇじょうぶ博士
「あるいは、音楽的な訓練を受けていない人は、16分音符のズレや音符のスキップに気づかないのかもしれないでやんす。」
かっぱ
「それやったら、プロの音楽家が指摘しとる意味があるっちゅうことやな。素人には分からん問題を明らかにしとるわけや。」
ずん
「つまり、音楽やってる人ほどこのMVにイライラするってことなのだ?」
やきう
「当たり前やろ。料理人が不味い料理見たらイライラするのと同じや。専門家ほど細部が気になるんや。」
でぇじょうぶ博士
「しかし、これは生成AIの現在地を示す重要な事例でもあるでやんす。『できること』と『できていること』の差が明確でやんす。」
かっぱ
「現在地示すんはええけど、それを正式なMVとして公開すんのはどうなんや。実験映像として出すべきやったんちゃうか。」
ずん
「じゃあ、パソコン音楽クラブは別のMVを作り直すべきなのだ?」
やきう
「作り直したところで、もう印象悪なっとるからなあ。6年待たせたあげく、これやからな。」
でぇじょうぶ博士
「時間の問題も重要でやんすね。2019年のリリースから6年...その間に期待値が膨らみすぎたのかもしれないでやんす。」
かっぱ
「期待値の問題ちゃうで。単純にクオリティが低いんや。1年で作ろうが10年で作ろうが、これはあかん。」
ずん
「でも、記事の筆者も『好きなところがある』って言ってるのだ。全否定してるわけじゃないのだ。」
やきう
「好きなところがあっても、全体としてダメやったら意味ないやろ。100点満点のテストで部分点もらって喜ぶんか?」
でぇじょうぶ博士
「しかし、サビ直前のスローモーションや、画面分割の使い方は評価されているでやんす。全てが失敗というわけではないでやんすよ。」
かっぱ
「部分的に成功しとっても、基本ができてへんかったら台無しや。料理で言うたら、盛り付けは綺麗やけど味が薄いみたいなもんやで。」
ずん
「じゃあ、今後AIでMV作る人たちは、この失敗から何を学ぶべきなのだ?」
やきう
「まず音楽理論勉強しろや。16分音符がどうとか、そういう基本的なことから始めんとあかんで。」
でぇじょうぶ博士
「あるいは、音楽家とAI技術者のコラボレーションが必要でやんすね。それぞれの専門性を持ち寄らないと、こういう中途半端なものができるでやんす。」
かっぱ
「せやな。餅は餅屋や。AI使うんはええけど、音楽の専門家がちゃんとチェックせなあかん。」
ずん
「でも、それじゃあAIの意味ないんじゃないのだ?結局人間が全部チェックするなら...」
やきう
「せやから最初から人間が作れって話やねん。AIに任せきりにするから、こういうゴミができるんや。」
でぇじょうぶ博士
「ゴミは言い過ぎでやんすが、確かに『道具』としてのAIの使い方を間違えた例ではあるでやんすね。」
かっぱ
「間違えたっちゅうより、過信しとったんやろな。AIならなんでもできるって思い込んどったんや。」
やきう
「『新しい技術を使えば良い作品ができる』っちゅう幻想を捨てろってことやな。大事なんは技術やのうて、センスや。」
でぇじょうぶ博士
「そして、基本的な技術の習得は省略できないということでやんすね。AIは魔法の杖ではないでやんす。」
かっぱ
「ほんまそれな。基本がでけへん奴がAI使っても、結局基本ができてへんもんしかでけへんのや。」
ずん
「なるほどなのだ...つまり、ボクがAI使ってもボクレベルのものしかできないってことなのだ...って、これ結局ボクが一番ダメってことじゃないのだ!?」