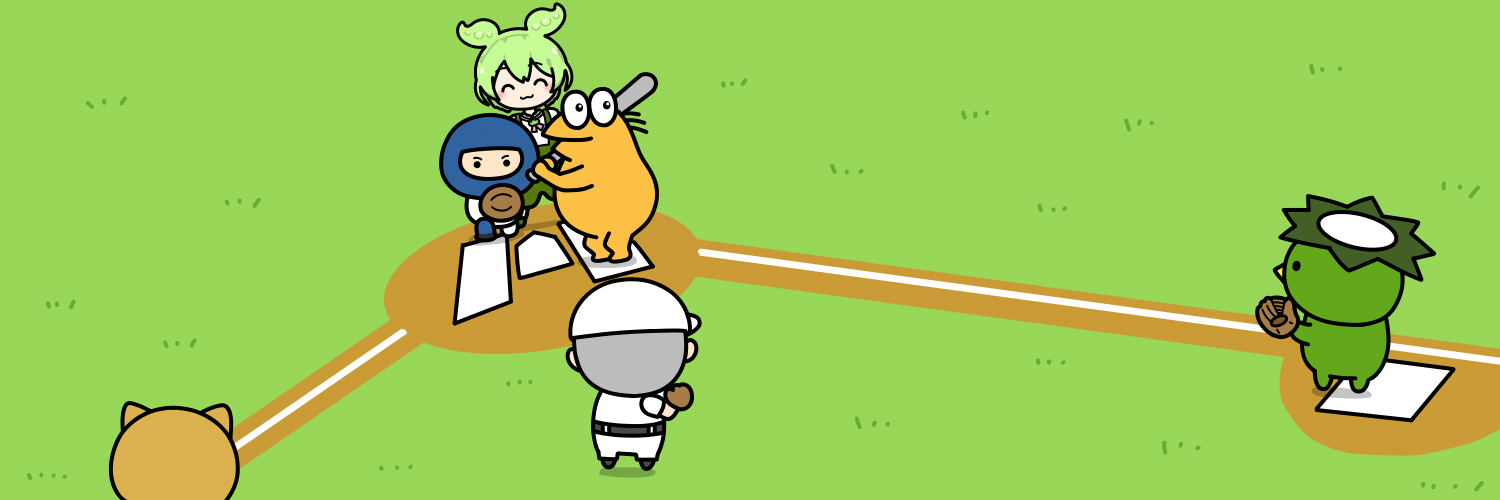# 中国のアニメ規制(上)
子供向けエヴァンゲリオンの悲劇
ずん
「ねえねえ、中国でエヴァが『天鷹戦士』って改題されたって本当なのだ?まさかハトと戦う話になったのかのだ?」
でぇじょうぶ博士
「やんすねぇ。しかも2001年に放送された時は、宗教要素全削除、キスシーンは『歌を歌おう』に差し替え、哲学的独白もバッサリカットでやんす。まるで骨を抜いた魚を『これが刺身だ』と出すようなもんでやんすよ。」
かっぱ
「ほんで視聴者ブチギレたんやろ?当たり前や。みんな海賊版で原作知っとったんやから。」
ずん
「えっ、じゃあ最初から観るなってことなのだ?」
かっぱ
「違うがな。期待してテレビつけたら、碇シンジが陽気な熱血少年になっとったんや。そら怒るわ。」
でぇじょうぶ博士
「そもそも中国では『アニメ=子ども向け』という認識が2000年代から根付いてるでやんす。だからR-15とかPG12みたいな区分が存在しないでやんす。全部『未成年に悪影響』で一律規制でやんすよ。」
ずん
「つまり、大人が観るアニメという概念がないのだ?」
でぇじょうぶ博士
「やんす。80〜90年代は『一休さん』や『ドラゴンボール』がゴールデンタイムで流れてたでやんす。遼寧の吹き替えチームと広東テレビの黄金コンビでやんすね。でも2000年に政府が『輸入アニメ審査強化』を通達して、全部終わったでやんす。」
かっぱ
「そのタイミングでエヴァが来たんか。最悪やな。」
でぇじょうぶ博士
「しかも人手不足で一人何役も担当、納期に追われて深夜作業の連続でやんす。試写版出したら『子どもに不適切』で却下。スタッフは気が狂いそうになったでやんすよ。」
ずん
「でも結局放送したんでしょ?どうやって通したのだ?」
でぇじょうぶ博士
「『使徒』を『使者』に変更、『人類補完計画』みたいな難解な用語は全部簡略化、物語を『少年少女が怪獣と戦う単純な話』に作り替えたでやんす。まるでシェイクスピアの戯曲を小学生の学芸会にするようなもんでやんすよ。」
かっぱ
「それで『新世紀ハエ戦士』って呼ばれたんやな。ハエって...。」
ずん
「でも待って。海賊版が先に出回ってたなら、そもそも吹き替え版作る意味なかったんじゃないのだ?」
でぇじょうぶ博士
「鋭いでやんすね、ずん君。でも契約を結んだ以上、配給元の催促もあって中止できなかったでやんす。進むも地獄、引くも地獄でやんすよ。」
かっぱ
「それにしても、『カードキャプターさくら』で『好きだよ』を『いい子だと思ってた』に変えるとか、もはや別の作品やん。」
ずん
「じゃあ中国の子どもたちは恋愛を知らずに育つのだ?」
でぇじょうぶ博士
「いやいや、現実では普通に恋愛してるでやんす。ただアニメでは『早すぎる恋愛』として規制されるだけでやんす。まるでタバコのパッケージに『喫煙は健康に悪い』と書いて売るようなもんでやんすね。」
かっぱ
「ほんで、この失敗がきっかけで日本アニメの公式輸入が終わったんか。」
でぇじょうぶ博士
「やんす。その後は『字幕組』という非公式グループがネットで字幕つけて配信する時代になったでやんす。皮肉なことに、規制を強化したら違法ルートが栄えたでやんすよ。」
ずん
「つまり、真面目にやろうとした人たちが一番損したってことなのだ?」
かっぱ
「せや。遼寧のスタッフはボロクソに叩かれて、視聴者は『作品をめちゃくちゃにした』って怒り狂ったんや。誰も得してへん。」
でぇじょうぶ博士
「そして2024年、『シン・エヴァンゲリオン』がまた『天鷹戦士』として公開されるでやんす。歴史は繰り返すでやんすね。まるでタイムループに囚われた碇シンジのように。」
でぇじょうぶ博士
「可能性は高いでやんす。ただし今はネット時代でやんすから、みんな原作を知ってるでやんす。炎上は避けられないでやんすね。」
かっぱ
「ほんま、『アニメは子ども向け』っていう固定観念が全ての元凶やな。」
ずん
「でも博士、子どもにエヴァ観せたら、確かにトラウマになりそうなのだ...。」
でぇじょうぶ博士
「やんすねぇ。だからこそ年齢制限という仕組みが必要でやんす。でも中国にはそれがないから、『全部禁止』か『全部子ども向けに改変』の二択しかないでやんすよ。」
かっぱ
「極端すぎるわ。グレーゾーンがないんやな。」
ずん
「じゃあボクが中国でアニメ配信会社作ったら、きっと成功するのだ!だって誰もやってないもん!」
でぇじょうぶ博士
「...やんす、それはおいらの計算によると...いや、ずん君が会社作る前に規制で潰されるでやんす。」
かっぱ
「そもそもお前、会社なんか作れへんやろ。起業の『起』の字も書かれへんくせに。」
ずん
「むぅ...じゃあボクは日本でエヴァを自由に観られることに感謝するのだ!」