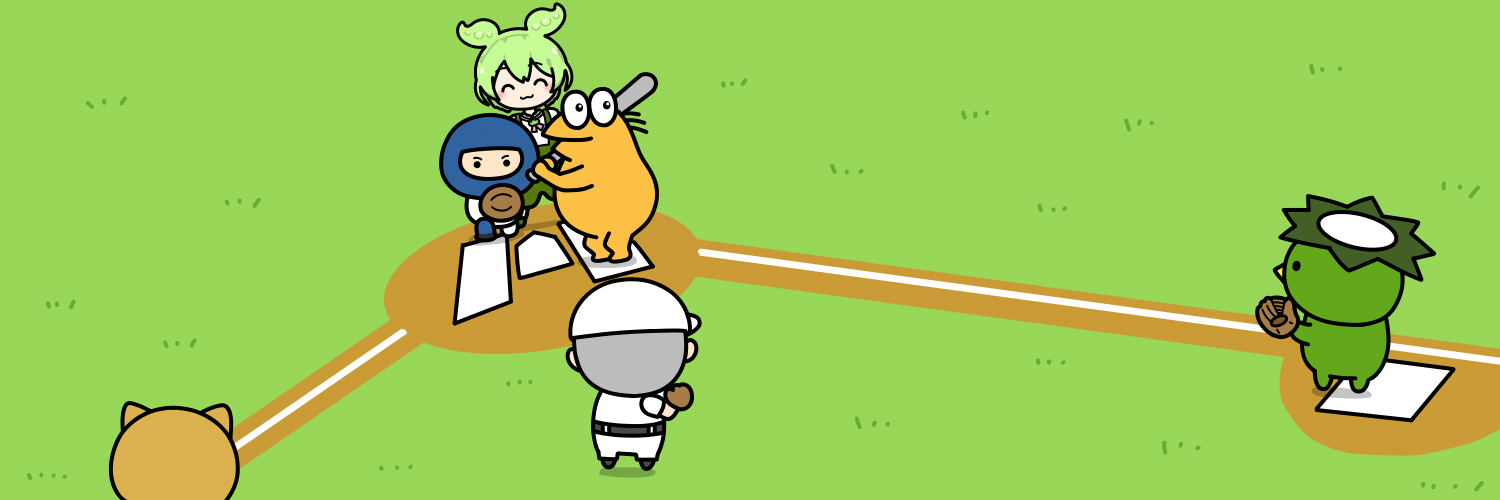ずん
「なんか監察医が話題になっているのだ。死体を切り刻む仕事って、やばくないっすか?」
でぇじょうぶ博士
「ずん君、監察医は『死体を切り刻む』んじゃなくて、『死体の声を聞く』でやんす。まるで通訳のようなもんでやんす。」
やきう
「通訳?死体が何か喋るんか?ワイには『うぅ...』としか聞こえへんで。」
でぇじょうぶ博士
「喉に砂があるか、爪に皮膚片が残ってるか...そういう痕跡から死因を解明するでやんす。死体はウソをつかないでやんすからね。」
かっぱ
「ほんで、剪定ばさみでろっ骨切るんやろ?園芸用具で人間バラすとか、狂気やん。」
でぇじょうぶ博士
「...剪定ばさみは骨を切るのに最適な道具でやんす。医療用メスより効率的でやんすよ。」
ずん
「え、ホームセンターで売ってるやつで人間切れるのだ?ボクでもできそうなのだ。」
やきう
「お前が切るんは段ボールまでや。ろっ骨とか絶対無理やろ。」
でぇじょうぶ博士
「そもそも監察医は不足してるでやんす。需要に対して供給が全然追いついてないでやんすよ。」
かっぱ
「そら当たり前やろ。誰が好き好んで死体相手にするねん。」
ずん
「でもボク思ったのだ。死体って文句言わないから、接客業より楽なんじゃないっすか?」
でぇじょうぶ博士
「むしろ死体は最も正直な証人でやんす。生きてる人間みたいに嘘をつかないでやんすからね。まるで究極の正直者でやんす。」
かっぱ
「せやな。生きてる奴らはみんな嘘つきやからな。死んでからやっと本音出すんやろ。」
ずん
「じゃあ監察医って、死んだ人の最後の願いを叶える仕事なのだ?なんかカッコいいのだ。」
やきう
「急に美談にすな。お前さっき『楽そう』って言うたやろが。」
でぇじょうぶ博士
「記事では水死体に見えた女性が実は殺人被害者だった例が紹介されてるでやんす。衣服を着てたことと喉の砂が決め手でやんすね。」
でぇじょうぶ博士
「溺れる時は必死でもがくでやんすから、服が水の抵抗で脱げることが多いでやんす。着衣のままってのは不自然でやんすよ。」
ずん
「へー。じゃあ川で死体見つけたら、まず服チェックすればいいのだ。ボクも探偵になれそうなのだ。」
やきう
「お前が最初に見つけるんは職場やろ。ニート卒業してから言え。」
かっぱ
「しかし喉の砂って、どんだけ微量やねん。そんなん気づくか普通?」
でぇじょうぶ博士
「そこが監察医の専門性でやんす。人体が死の瞬間に示す反応を知り尽くしてるでやんすからね。まるでミクロン単位で世界を見てるようなもんでやんす。」
ずん
「でも博士、監察医が足りないって問題なのだ。誰か増やせばいいじゃないっすか。」
でぇじょうぶ博士
「結局そこでやんすか...。でも実際、監察医になるには医師免許に加えて法医学の専門知識が必要でやんす。なかなか育成が難しいでやんすよ。」
かっぱ
「そら大変やわ。しかも給料そんな良くないんやろ?誰がやるねん。」
ずん
「じゃあAIにやらせればいいのだ!画像認識とかで異常検知できそうなのだ。」
やきう
「お前、何でもAIって言えば解決すると思っとるやろ。」
でぇじょうぶ博士
「確かにAIは補助ツールとして有用でやんすが、最終判断は人間の経験と直感が必要でやんす。死体の『語り』を聞くのは、まだ人間にしかできない芸当でやんすよ。」
かっぱ
「つまり、これからも人間が剪定ばさみ持ってろっ骨切り続けるわけやな。地味にホラーやわ。」
ずん
「ボク、今日から剪定ばさみ見るたびにろっ骨思い出しそうなのだ...」
でぇじょうぶ博士
「監察医は社会の安全を守る縁の下の力持ちでやんす。遺体から真実を読み解き、犯罪を暴くでやんすからね。」
ずん
「じゃあ監察医って、死んだ人の最後の代弁者なのだ。ちょっと感動したのだ...でも、やっぱりボクは生きてる人相手の仕事がいいのだ!死体と話すより、ずんだ餅と話す方が楽しいのだ!」