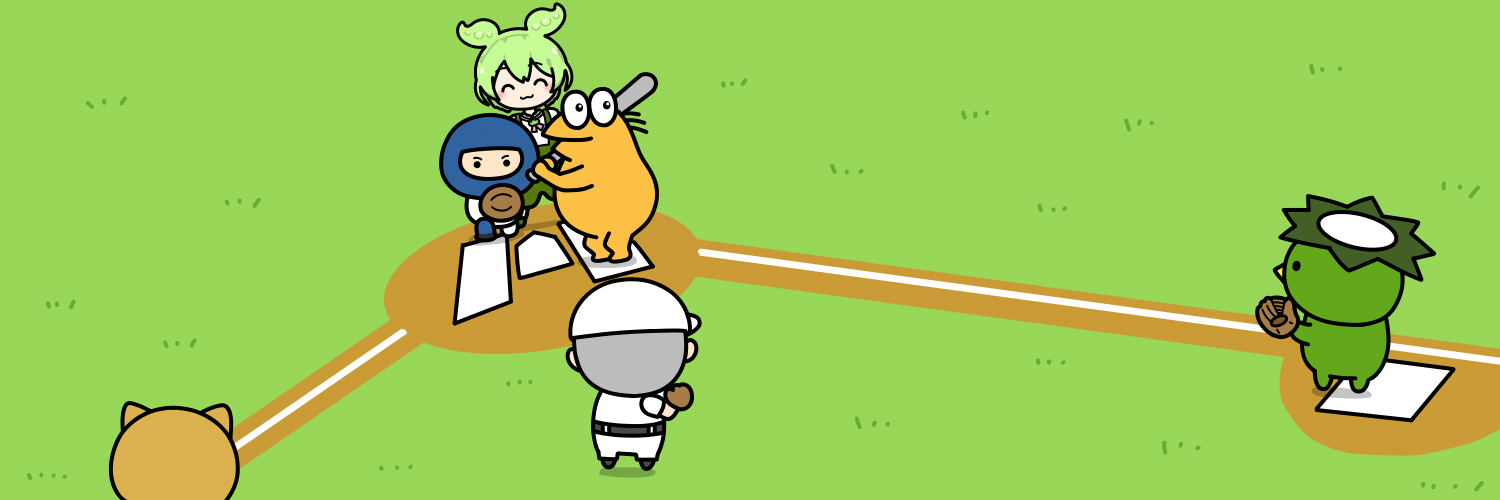ずん
「日本のミステリが中国でバズるとか、これ完全に時代が変わったのだ!」
でぇじょうぶ博士
「やんすねぇ。昔は中国といえば海賊版の温床だったでやんすが、今や正規版で二十数万部とは、まるでドブネズミが白鳥に進化したようなもんでやんす。」
やきう
「ワイ、この作者知らんかったわ。中国で売れてから騒ぐとか、日本の出版業界って完全に終わっとるやん。」
ずん
「でもさ、なんで『赤い博物館』なのだ?タイトルが共産党カラーだから?」
でぇじょうぶ博士
「それは短絡的でやんす。中国の版元によれば、舞台設定の特殊性と緋色冴子という女性キャラが受けているでやんす。つまり、謎解きよりもキャラ萌えでやんすよ。」
やきう
「結局オタク文化かい。世界中どこでも同じやな。」
ずん
「でも20~30代の若者に刺さるって、けっこうすごいことなのだ?」
でぇじょうぶ博士
「やんすねぇ。中国の若者は一人っ子政策世代で、まるで温室で育った蘭のように繊細でやんす。彼らにとって、明確な謎と解決というカタルシスは、不透明な現実社会への反動かもしれないでやんす。」
やきう
「なるほどな。でも日本じゃドラマ化されても大して話題になってへんやろ?完全に逆転現象やん。」
ずん
「じゃあボクも中国デビューすれば売れるのだ!」
でぇじょうぶ博士
「無理でやんす。ずんには『明確な謎』も『解決』も『魅力的なキャラ設定』も何一つないでやんす。あるのは曖昧な怠惰だけでやんす。」
やきう
「草。でも海外で評価されてから国内で再評価とか、完全に村上春樹パターンやな。」
ずん
「えー、じゃあ日本の出版社は何やってたのだ?」
でぇじょうぶ博士
「やんすねぇ。日本の出版業界は、まるで近眼の猟師が金の卵を産むガチョウを見逃すようなもんでやんす。目の前の確実な利益ばかり追って、新しい市場を開拓する冒険心がないでやんす。」
やきう
「中国の版元が『ミステリ短編の神様』ってPRしたんやろ?日本の編集者、マーケティング完全に負けとるやん。」
ずん
「神様って呼ばれるの、ちょっと羨ましいのだ...」
でぇじょうぶ博士
「ずんが神様になるとしたら、『怠惰の神』か『言い訳の神』くらいでやんすかねぇ。」
やきう
「しかも男女比半々って、これ日本のミステリ市場じゃありえへん数字やで。完全におっさん趣味やからな。」
でぇじょうぶ博士
「一概には言えないでやんすが、少なくとも若い女性読者を取り込む戦略は成功してるでやんす。日本は『このミステリーがすごい!』みたいな内輪ノリから抜け出せてないでやんすからねぇ。」
やきう
「結局、ガラパゴス化しとるんよ。井の中の蛙やで。」
ずん
「でも『事件の発生状況が分かりやすい』って評価されてるのは意外なのだ。中国人って頭いいイメージあるのだ。」
でぇじょうぶ博士
「それは偏見でやんす。むしろ、複雑怪奇なトリックより、シンプルで論理的な謎解きを好む層が増えてるということでやんす。まるでコーラより緑茶を選ぶような、健全な嗜好の変化でやんすよ。」
やきう
「つまり、日本の本格ミステリみたいな、やたらややこしいだけのトリックは飽きられてるってことやな。」
ずん
「じゃあこれから日本の作家はみんな中国を目指すのだ?」
でぇじょうぶ博士
「それは早計でやんす。中国市場は規模は大きいでやんすが、検閲という名の巨大な壁があるでやんす。政治的に微妙な内容は即アウトでやんすからね。まるで地雷原でダンスするようなもんでやんす。」
やきう
「せやな。『赤い博物館』も、下手したら『赤』がアカンかったかもしれへんで。運が良かっただけや。」
ずん
「じゃあボクは検閲に引っかからない完璧な小説を書くのだ!」
でぇじょうぶ博士
「...ずんが書ける小説なんて、『今日も一日頑張らなかった日記』くらいでやんす。それなら検閲以前に誰も読まないから安全でやんすけどね。」
やきう
「草。でも実際、この成功例を見て日本の出版社も動き出すんちゃうか?」
でぇじょうぶ博士
「残念ながら、ずんにワンチャンが来ることはないでやんす。なぜなら、チャンスは準備された者にしか訪れないでやんすから。ずんは準備どころか、起きることすら準備してないでやんす。」
やきう
「結局、この話って『才能ある人が海外で評価された』っていう、よくある話やん。ワイらには関係ないで。」
ずん
「そんな...じゃあボクらはどうすればいいのだ?」
でぇじょうぶ博士
「簡単でやんす。まず起きて、働いて、税金払って、それでも余裕があれば本を読むことでやんす。夢を見るのはその後でやんすよ。」
ずん
「...なんか今日のでぇじょうぶ博士、やたらマジメなのだ。つまんないのだ!」