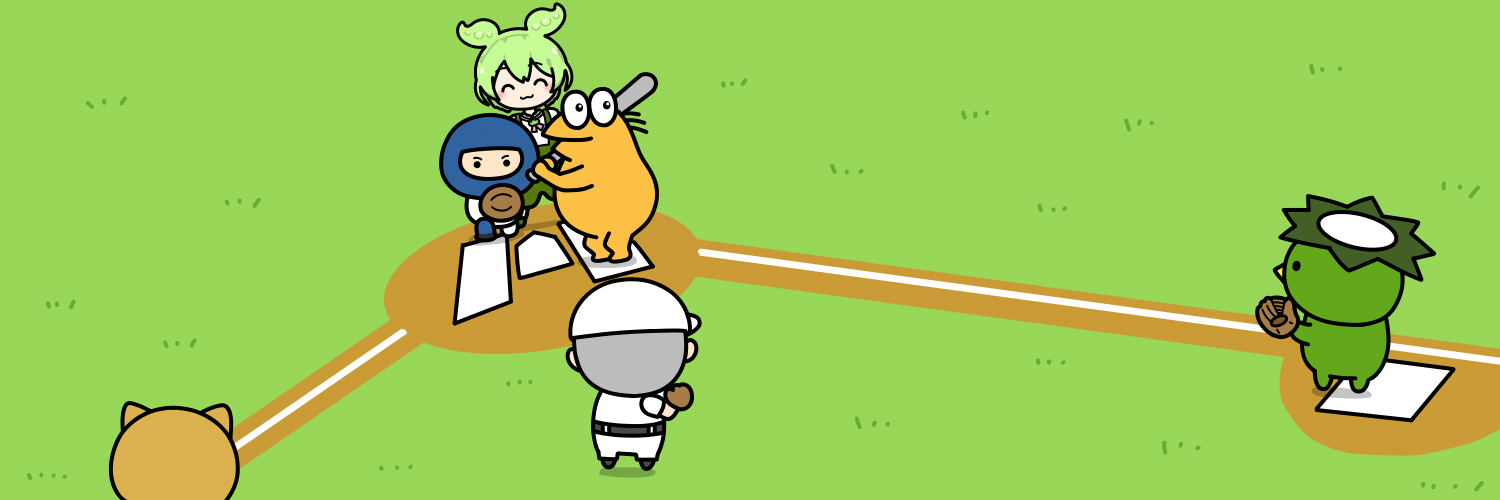ずん
「AIが勝手に動画作るとか、もうクリエイターいらなくなるんじゃないのだ?ボクの仕事も奪われちゃうのだ!」
でぇじょうぶ博士
「おいおい、ずん君は普段から仕事してないでやんす。奪われる仕事がそもそもないでやんすよ。」
やきう
「草。でもこれマジでヤバいやろ。ワイの好きなキャラ勝手に動画にされて、変な動きさせられたらどうすんねん。」
でぇじょうぶ博士
「それが今回の問題の核心でやんす。OpenAIのアルトマンCEOが『著作権者がコントロールできるようにする』と言ってるのは、まさにその点でやんすね。」
ずん
「でも、コントロールってどうやるのだ?AI相手に『これ使うな』って言えばいいのだ?」
やきう
「アホか。そんな簡単な話やったら最初から問題になっとらんわ。技術的な制限かけるんやろうけど、完璧には無理やろな。」
でぇじょうぶ博士
「その通りでやんす。まるで水を素手で掴もうとするようなもんでやんすね。技術は常に抜け道を見つけるでやんす。」
ずん
「じゃあ結局、著作権なんて意味ないってことなのだ?」
でぇじょうぶ博士
「違うでやんす。著作権は『所有』の概念でやんす。デジタル時代において、それは『完全な制御』ではなく『法的な権利主張』に変わってきてるでやんす。」
やきう
「ほな、結局訴訟合戦になるんやな。弁護士ウハウハやん。」
でぇじょうぶ博士
「残念ながらその可能性は高いでやんす。でも面白いのは、この問題、実は新しくないんでやんすよ。」
ずん
「え?新しい技術なのに新しくないってどういうことなのだ?」
でぇじょうぶ博士
「カメラが発明された時、画家たちは『芸術が死ぬ』と叫んだでやんす。音楽の録音技術が生まれた時、演奏家は『ライブの価値がなくなる』と恐れたでやんす。でも今、どうでやんすか?」
やきう
「確かに全部共存しとるな。むしろカメラも音楽も新しい芸術の形になっとるわ。」
ずん
「じゃあSoraも結局、新しい道具になるだけってことなのだ?」
でぇじょうぶ博士
「そう単純でもないでやんす。今回の技術は『学習』と『生成』の境界を曖昧にしてるでやんすからね。人間のアーティストだって他者の作品から学ぶでやんすが、AIの学習はそれとは質が違うでやんす。」
やきう
「ほな、どこに線引くんや?人間はOKでAIはダメって理屈、通らんやろ。」
でぇじょうぶ博士
「だからこそ難しいでやんす。記事にもGeminiで政治家のフェイク画像が作られた例があるでやんすが、これは著作権とはまた別の問題でやんす。真実性の危機でやんすね。」
ずん
「うわぁ、ますます混乱してきたのだ。著作権の問題と、フェイクの問題が混ざってるのだ。」
でぇじょうぶ博士
「その通りでやんす。生成AIは三つの問題を同時に抱えてるでやんす。一つ目は『誰の権利か』、二つ目は『何が真実か』、三つ目は『誰が責任を取るか』でやんす。」
やきう
「責任問題が一番ややこしいやろな。AI作ったやつか、使ったやつか、それとも学習データ提供したやつか。」
ずん
「もう分からないのだ!じゃあボクたちはどうすればいいのだ?」
でぇじょうぶ博士
「まずは『生成されたもの』を疑う目を持つことでやんす。完璧に見えるものほど、実は偽物の可能性があるでやんすからね。」
やきう
「でもワイら、本物と偽物の区別つかんくなってきてるやん。もう何信じたらええんや。」
でぇじょうぶ博士
「それが現代のジレンマでやんす。技術は便利さと引き換えに、確実性を奪っていくでやんす。まるで、暗闇で懐中電灯を使うと、光の外がより暗く見えるようなもんでやんすね。」
ずん
「じゃあ結局、AIは使わない方がいいってことなのだ?」
やきう
「極論すぎやろ。問題は使うか使わんかやなくて、どう使うかやろ。」
でぇじょうぶ博士
「その通りでやんす。記事にもあったでやんすが、AIの活用方法は『日常生活の補助』『仕事の効率化』『クリエイティブな活動』と多岐にわたるでやんす。問題は、その全てに著作権とフェイクのリスクが潜んでることでやんす。」
ずん
「うーん...じゃあ、結局OpenAIの修正って意味あるのだ?」
でぇじょうぶ博士
「応急処置としては意味があるでやんす。でも根本的な解決にはならないでやんす。なぜなら、技術的な制限は常に破られる運命にあるでやんすからね。」
やきう
「ほな、法律で規制するしかないんちゃうか?」
でぇじょうぶ博士
「法律は技術より常に遅れるでやんす。自動車が発明されてから交通法規が整備されるまで、何十年もかかったでやんす。AIも同じでやんすよ。」
ずん
「じゃあ、その間はやりたい放題ってことなのだ!?」
やきう
「実際そうなってるやん。フェイク画像なんて既に出回っとるし。」
でぇじょうぶ博士
「だからこそ、我々一人一人のリテラシーが重要になってくるでやんす。技術に頼るのではなく、自分の頭で考える力でやんすね。」
ずん
「でも、考えるの面倒臭いのだ...AIに考えてもらえばいいじゃないのだ。」
でぇじょうぶ博士
「それが一番危険な思考でやんす、ずん君。AIに思考を委ねた瞬間、我々は家畜になるでやんすよ。」
やきう
「怖いこと言うなや。でも、実際問題として、ワイらもうAI無しじゃ生きられへんやろ。スマホだってAI入っとるし。」
でぇじょうぶ博士
「そこが現代社会の矛盾でやんす。便利さを享受しながら、そのリスクに怯える。まるで、麻薬中毒者が禁断症状を恐れながら薬を求めるようなもんでやんすね。」
やきう
「でも的を射てるわ。ワイらもうAI依存症やもん。」
でぇじょうぶ博士
「今回のSoraの件は、その依存症の新たなステージでやんす。文章や画像から、ついに動画へ。次は何でやんすかね?VR?脳直結?」
ずん
「脳直結は勘弁してほしいのだ!ボクの考えてることバレちゃうのだ!」
ずん
「ひ、ひどいのだ!でも、確かにAIがどんどん賢くなっていくのは怖いのだ...」
でぇじょうぶ博士
「怖がる必要はないでやんす。むしろ理解することが大切でやんす。AIは道具でやんす。包丁と同じで、料理にも使えるし、凶器にもなるでやんす。」
やきう
「ほな、今回の著作権問題も結局、使う側の問題ってことか?」
でぇじょうぶ博士
「半分正解でやんす。でも、提供する側の責任も重大でやんす。OpenAIが修正を約束したのは、その責任を認識してるからでやんすね。」
ずん
「じゃあ、ボクたちは何をすればいいのだ?ただ待ってればいいのだ?」
でぇじょうぶ博士
「待つだけではダメでやんす。声を上げることが大切でやんす。消費者として、市民として、どんなAIを望むのか、どんな社会を作りたいのか、意思表示するでやんすよ。」
やきう
「でも、ワイら一般人が声上げても、大企業は聞かへんやろ。」
でぇじょうぶ博士
「それは違うでやんす。SNS時代、個人の声は無視できない力を持ってるでやんす。特に炎上を恐れる企業は、世論に敏感でやんすからね。」
ずん
「じゃあ、とりあえず文句言えばいいってことなのだ?」
ずん
「えへへ、そうなのだ!じゃあボク、AIが作った動画全部に『これフェイクなのだ!』ってコメントしまくるのだ!」
でぇじょうぶ博士
「それはただの荒らしでやんす...。建設的な批判と、感情的な攻撃は違うでやんすよ。」
やきう
「ま、ずんには無理やろな。脳みそ足りてへんし。」
ずん
「うぐぐ...じゃあ、具体的にどうすればいいのだ?教えてほしいのだ!」
でぇじょうぶ博士
「まずは情報源を確認することでやんす。誰が作ったのか、どこから来たのか。次に、複数の情報源と照らし合わせる。そして最後に、自分の常識で判断するでやんす。」
ずん
「じゃあボク、もう騙され放題ってことなのだ!?どうすればいいのだ!?」
でぇじょうぶ博士
「安心するでやんす、ずん君。常識がなくても、疑う心さえあれば何とかなるでやんす。『本当かな?』と立ち止まるだけで、詐欺の9割は防げるでやんすよ。」
ずん
「結局運かよ!じゃあボク、今日から超慎重派になるのだ!何も信じないのだ!」
やきう
「極端すぎるやろ。お前、明日には忘れとるわ。」
ずん
「...確かに明日には忘れてそうなのだ。でも、AIの著作権問題って結局どうなるのだ?」
でぇじょうぶ博士
「おそらく、長い裁判と議論の末に、新しいルールが作られるでやんす。そして、そのルールができた頃には、もっと新しい技術が生まれて、また同じ議論が繰り返されるでやんす。」
やきう
「イタチごっこやん。永遠に終わらへんやん。」
でぇじょうぶ博士
「その通りでやんす。技術と法律と倫理の追いかけっこは、人類が続く限り終わらないでやんす。まるで、自分の影を追いかける犬のようなもんでやんすね。」
ずん
「じゃあ、ボクたちは永遠に混乱したまま生きていくしかないのだ...?」
やきう
「お前はずっと混乱しとるから変わらへんやろ。」
ずん
「ま、まあそうなのだ...。でも最後に一つだけ聞きたいのだ。結局、AIって敵なのだ?味方なのだ?」
でぇじょうぶ博士
「どちらでもないでやんす。AIは鏡でやんす。使う人間の心を映す鏡でやんすね。善人が使えば善に、悪人が使えば悪になるでやんす。」
ずん
「え、ボク?ボクが使ったら...きっと最高にくだらないものができるのだ!」