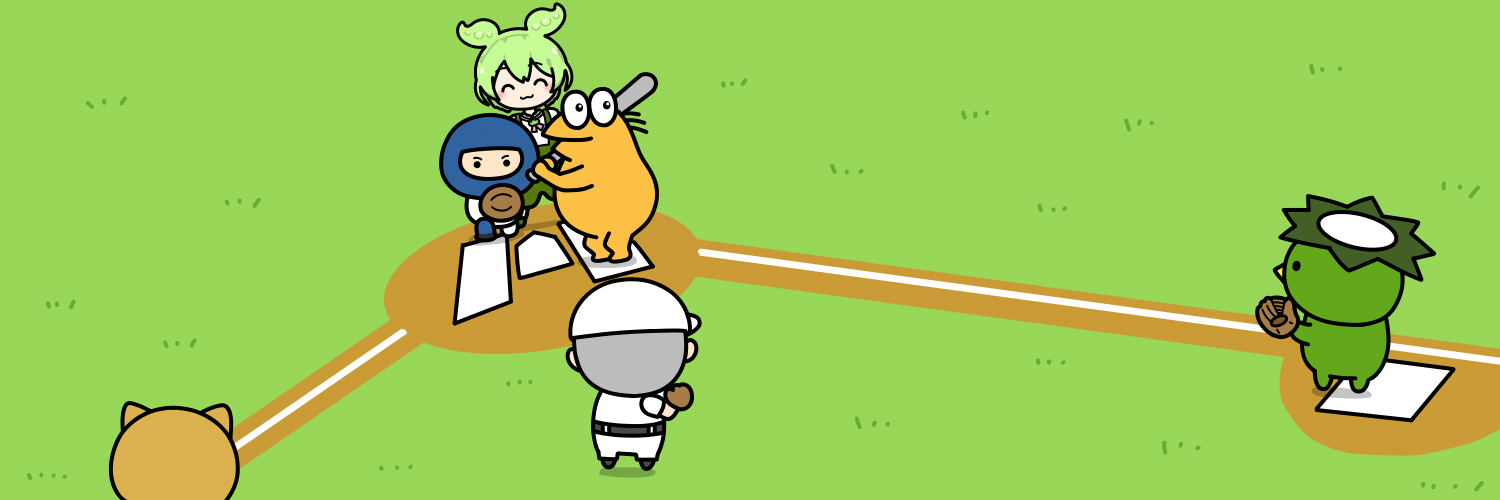ずん
「最期ってそんなにあっけないものなのだ?なんか、ドラマとか映画みたいに劇的じゃないのだ?」
でぇじょうぶ博士
「そうでやんすね。実際の死というのは、テレビドラマのように感動的な遺言があるわけでもなく、まるで電池が切れるかのように静かに訪れるものでやんす。」
やきう
「ワイの電池も切れかけとるわ。充電する気力もないけどな。」
ずん
「でも原発不明がんって、なんでわからないのだ?医者って万能じゃないのだ?」
でぇじょうぶ博士
「医者が万能なら、おいらがモテないことも治療できるはずでやんす。でも現実は違うでやんす。原発不明がんは全がん患者の1~3%程度で、がんの原発巣が特定できないまま転移だけが見つかる厄介な病気でやんす。」
やきう
「つまり犯人不明の殺人事件みたいなもんやな。証拠だけあって、犯人がどこにおるかわからへん。」
でぇじょうぶ博士
「治療は可能でやんすが、原発がわからないということは、最適な治療法を選べないということでやんす。まるで地図なしで宝探しをするようなものでやんす。」
やきう
「地図なしで人生歩いとるワイには親近感湧くわ。」
ずん
「でも160日って、余命数週間って言われてたのに長生きしたのだ?」
でぇじょうぶ博士
「そこが人間の生命力の不思議なところでやんす。医師の余命宣告というのは、あくまで統計的な予測に過ぎないでやんす。人間の意志や環境によって、その予測を大きく超えることもあるでやんす。」
やきう
「まあ医者の予測なんて、競馬の予想屋レベルやろ。当たったらラッキーや。」
でぇじょうぶ博士
「医療用麻薬は適切に管理されれば、がん性疼痛の緩和に非常に有効でやんす。痛みで苦しむより、意識は朦朧としても痛みから解放される方が、患者さんのQOL(生活の質)は高いでやんすよ。」
やきう
「ワイも人生の痛みから解放されたいんやけど、処方箋もろてええか?」
ずん
「でも意識が朦朧としちゃうってことは、最期にちゃんと会話できないってことなのだ?」
でぇじょうぶ博士
「そうでやんすね。痛みと意識のバランスをどう取るかは、終末期医療の永遠のジレンマでやんす。痛みを完全に取れば意識が遠のき、意識を保てば痛みに耐えなければならない。どちらを選ぶかは、患者さんと家族の価値観次第でやんす。」
やきう
「人生の最期まで選択を迫られるんやな。しかもどっち選んでも正解がないという地獄や。」
ずん
「自宅で看取るって大変そうなのだ。病院じゃダメなのだ?」
でぇじょうぶ博士
「在宅での看取りは、確かに家族の負担は大きいでやんす。24時間体制での介護が必要になるでやんすからね。でも住み慣れた場所で、愛する人に囲まれて最期を迎えられるというのは、患者さんにとって大きな安らぎになるでやんす。」
やきう
「ワイは誰にも看取られへんから、孤独死確定やな。まあ、それも一つの人生や。」
ずん
「訪問看護師さんって、そんなに頼りになるのだ?」
でぇじょうぶ博士
「訪問看護師は在宅医療の要でやんす。医療的なケアはもちろん、家族の精神的なサポートも行うでやんす。この記事でも『これ以上は無理だ』と医師に告げたのは訪看でやんすね。家族が限界に達する前に、プロが判断を下すのは重要でやんす。」
やきう
「つまり家族だけで抱え込むなってことやな。まあワイは抱え込む家族もおらんけど。」
ずん
「でも最期の朝、『今日も生きていてくれた』って毎朝確認するの、辛すぎるのだ...」
でぇじょうぶ博士
「そうでやんすね。これは看取りをする家族の壮絶な現実でやんす。毎朝、生きているか死んでいるかを確認するというのは、まるで綱渡りをしているような精神状態でやんす。いつ終わるかわからない緊張感の中で、日々を過ごすわけでやんすから。」
やきう
「ワイも毎朝、生きてる意味あるんかって確認しとるで。答えは出てへんけどな。」
ずん
「ねえ博士、死ぬ瞬間って本当にわかるものなのだ?」
でぇじょうぶ博士
「興味深い質問でやんすね。この記事でも『様子が違って見えた』とありますが、長時間一緒にいる家族には、微妙な変化が感じ取れることが多いでやんす。呼吸のリズム、顔色、体温など、言葉にできない何かが伝わってくるでやんす。」
やきう
「ワイの人生も様子が違って見える瞬間があったけど、結局何も変わらんかったで。」
ずん
「希少がんとか難治がんって、どうして治療が難しいのだ?お金の問題なのだ?」
でぇじょうぶ博士
「お金だけの問題ではないでやんす。希少がんは患者数が少ないため、研究データが蓄積されにくく、有効な治療法の開発が遅れるでやんす。製薬会社も商業的に採算が取れないため、新薬開発に消極的になるでやんす。まさに医療の資本主義の闇でやんすね。」
やきう
「結局、金にならんもんは誰も研究せえへんってことやな。資本主義の犠牲者や。」
ずん
「じゃあボクが希少がんになったら、もう諦めるしかないのだ?」
でぇじょうぶ博士
「諦める必要はないでやんす。近年はゲノム医療の発達で、がんの遺伝子変異を解析し、それに合わせた治療を選択する『プレシジョン・メディシン』が発展してきているでやんす。希少がんでも、遺伝子レベルで共通点があれば、他のがんの治療薬が効く可能性もあるでやんす。」
やきう
「つまり医療もガチャゲーになってきたってことやな。当たり引けるかは運次第や。」
ずん
「この奥さんみたいに、160日間も看病し続けるの、ボクには絶対無理なのだ...」
でぇじょうぶ博士
「それは誰もが思うことでやんす。でも実際にその状況に置かれたら、人間は意外と強いものでやんす。愛する人を失いたくないという思いが、超人的な力を引き出すでやんす。おいらにはその経験がないから、想像でしかないでやんすけどね。」
やきう
「まあ博士はモテへんから、看取る相手もおらんしな。」
ずん
「でも結局、どんなに頑張っても死んじゃうなら、意味ないんじゃないのだ?」
でぇじょうぶ博士
「それは違うでやんす、ずん君。結果だけを見れば確かに死は避けられないでやんす。でも、その過程で過ごした時間、交わした言葉、触れ合った温もりは、残された人の心に永遠に刻まれるでやんす。人間の価値は、生きた長さではなく、どう生きたか、どう向き合ったかにあるでやんす。」
やきう
「博士、たまにはええこと言うやんけ。でもワイの人生には刻まれるもんが何もあらへんけどな。」
ずん
「うーん...じゃあボクも、いつか誰かを看取る日が来るかもしれないのだ...って、ちょっと待つのだ!ボクには看取る相手がいないのだ!これは大問題なのだ!まずは彼女作りから始めないといけないのだ!でも看取られるためだけに恋愛するって、完全に打算的すぎるのだ!!」